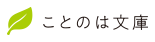丸くて甘い冥土のお土産
「小百合さん。私、食べたいものがあるの」
小百合がそう声をかけられたのは、厳かなお葬式が始まったばかりのこと。
目の前の祭壇に飾られた遺影写真と同じ顔のお婆さんが、喪服姿の小百合の隣に座り込み、じっと顔を見上げているのだ。
「食べなきゃ昇天なんてできないわ」
そして、脅すようにそう言うのである。
葛城小百合は除霊師だ。といっても無理やり祓ったり、乱暴をするわけではない。
「小百合さん、あなたって、幽霊の思い残した食べ物を食べて除霊してくれる……っていう噂を聞いたのだけど」
小百合の隣で目を輝かせる女性の名前は栄口という。小百合の住む波岸町、中でも歴史深いパン屋の先代オーナー。つい数日前、90歳の大往生で亡くなったばかり。大往生ということもあり、葬式はしめやかながらも賑やかで、玄孫たちの声も華を添えている。
「えっと。もちろんお手伝いしますよ」
小百合はご焼香を済ませると、慣れないヒールを履いて家の外に飛び出した。
栄口はニコニコと小百合のあとを付いてくる。葬式から主役を引っこ抜いていいものか、迷ったのは一瞬だけだ。思い残しに足を引っ張られ、こちらに留まらせるほうが家族はずっと悲しむはずである。
「じゃあ。どうぞ、栄口さん、私の中へ」
だから小百合は腕を広げ、目を閉じた。
焼香の香りと湿った匂いの染み付く喪服に手を添え、栄口はそっと小百合に重なる。
小百合の除霊法は、幽霊を自分自身に憑依させ、幽霊が未練を残した食べ物を一緒に食べて除霊する。そんなやり方。
「でもねえ。困ったことに……思い出せないのよ。食べたいものが」
……だから当の本人が「食べたいもの」を思い出せなければ、除霊などできるわけがないのだ。
「甘くて丸くてね……ふわふわなの。食べたことはないんだけど、最近よく話題になってて、一度は食べたいと思ってるうちに死んじゃったものだから……」
栄口は先程から同じことを繰り返し呟く。死んだ人が未練を思い出せないことはよくあることだ。生と死の間で名前が抜け落ち、未練だけが残ってしまうためである。
「名前がねえ、思い出せないの」
と、栄口は困ったようにため息をつく。
小百合の家にたどり着いたのは深夜前のこと。狭いアパートでは、小百合の除霊パートナーであるシェパード犬、ケンタが不機嫌そうに床に臥している。
「葬式に行ったと思ったら、本人を連れて戻ってくるとはな。何でも拾ってくるな」
ケンタは細長い口から愚痴を吐く。不思議なことにケンタは小百合と会話が交わせる。理由は不明だ。しかし世の中には不思議が多い。除霊師など、その最たるものである。
二人の会話を聞いた栄口は最初こそ驚いていたが、やがてすんなり受け入れた。
「食べたもの、早く思い出さなくっちゃ、相棒のワンコくんにも悪いわよね。ええっと、甘くてふわふわで……それで」
彼女の意識が、ふっとテレビに釘付けになり小百合の視線も引っ張られる。幽霊を体に憑依させると、共鳴するのだ。視線の共鳴、声の共鳴、そして記憶と感覚の共鳴。
「マリトッツォ!」
小百合と栄口は、テレビに映る愛らしい丸いものを見つめて、同時に叫んでいた。
「本物はブリオッシュを使うんですけど、今は時間もないから、栄口さんのお店で買ったこれを代わりに使います」
小百合は台所の食料庫から、ビニール袋を取り出し恭しく机に置く。
「うちのバターロール!」
「ちょっぴり甘いから、大好きなんです」
それは栄口パンの人気ナンバー1である、バターロール。数日前に手に入れていた柔らかなそれを、真ん中から2つに切る。
気泡多めに作られたパン生地は儚い柔らかさだ。しかし庖丁を押し付けたところで壊れない。芯の強いところが好きだった。
「夫が一番得意だったパンよ。夫が亡くなる前に娘婿に作り方を教えたの。そりゃ鬼コーチ。ようやく及第点を出した後に夫は死んだわ。もう10年も前の話だけど」
ふかふかのバターロールを見つめて栄口が懐かしそうに呟く。
「その鬼コーチのおかげで、味はそのまま。これを食べると今でも夫が生きているんじゃないか……って、そう勘違いしちゃうの」
テレビではまだマリトッツォの紹介が続いている。最近急に流行した、イタリア生まれの甘いお菓子。甘いパンに生クリームを山盛り詰めて、綺麗に整える。丸くて柔らかいものはきっと、世界共通の「おいしいもの」だ。
「なんだ、それ。シュークリームだろ」
「違うよ」
「違うわ」
ケンタの無粋なボヤキに栄口と小百合が同時にツッコミを入れる。そして栄口は楽しそうに笑うのだ。
「このワンコ、うちの人と同じようなことを言ってる。うちの人もね、流行りのお菓子の話をすると、アレに似てる、これに似てる。そう言って茶々ばっかり入れるのよ」
栄口の夫、つまり栄口パン屋の先代は気難しい男で有名だった。気難しい夫と無邪気な妻。性格は真反対だが、オシドリ夫婦として知られていた。
「きっとね、このお菓子のことも、ワンコと同じように言うと思うわ。それで私が返すのよ、あなた。それは違うわって」
夢見るような栄口の声を聞きながら小百合は生クリームを混ぜる。砂糖をたっぷり、バニラオイルを少々。
わざと固めに仕上げたそれを、ふかふかのバターロールにたっぷり挟み込む。
「さあ、一緒に食べよう」
小百合は大きな口を開き、零れそうな生クリームに噛み付く。しっかりとしたパン生地から溢れた生クリームが指に付くのも楽しい。ふかふかのパン生地は、クリームを吸って少し湿り、それも美味しい。
「それで私の話を聞いて、彼はいうの」
栄口が、満足するようなため息をつく。
「……なるほど、それは美味そうだなって」
「じゃあ、早く会いに行って伝えなきゃ」
「ありがとう、小百合さん。夫にいいお土産話ができたわ」
小百合の体がふわりと、軽く揺れた。体から何かが抜ける。倒れそうになる体を支えると、小百合の体から白く輝く光が抜けていくのが見える。それはやがて栄口の形となって、満足げな笑みを浮かべるのである。
「これぞ冥土の土産ってやつね」
ありがとう。彼女はそう言って、夜の静寂に消えていく。見送るように空を見る小百合の足に、ケンタの尻尾が力なく乗った。
「お嬢さん、俺はそんな爺さんみたいなことを言ってるか?」
「……時々ね」
ショックを受けるケンタに苦笑を返し、小百合は真っ黒な夜を見上げる。
まもなく栄口は世界で一番大好きな人に会い、最期の食事を語るのだ。甘い二人の再開を願いながら、小百合は柔らかなマリトッツォをそっとつついた。

彼女は食べて除霊する
- 著:みお
- イラスト:syo5
- 発売日:2021年8月20日
- 価格:770円(本体700円+税10%)
書店でのご予約はこちらの予約票をご利用ください