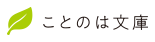さよならフライパン焼き肉
疲れたときは肉を食べるに限る。と、山田はふてくされたような声でそういった。
「一枚一枚ちんたら焼くんじゃないぞ。フライパンに切った山盛りの野菜と肉を入れてタレで煮るんだ。野菜から水分が出るだろ、そいつで薄まってちょうどよくなる」
山田の指示に従って、小百合が用意したのは大きなフライパンだ。熱したそこに、人参やキャベツ、もやし、そして牛肉。具で溢れそうなフライパンに注ぎ入れるのは甘めの焼き肉のタレ。油と野菜の水分がふつふつと湧き上がり部屋中に甘辛い香りが漂い始める。
「えっと。これって肉野菜炒め……?」
「焼き肉だよ、少なくとも俺の家では。ヤモメの作れる料理はこんなもんだ。この料理で娘を三人、立派に育てたんだ」
山田は自嘲気味にぼやく。
「俺だけなら肉だけでいいが、娘には野菜も食わさないといけないだろ」
小百合がフライパンに向き合っているのは、狭いアパートの一室、その台所。
振り返っても下を見てもどこにも小百合以外、人間の影はない。しわがれた声は、小百合の中から響いている。
「最期に食う飯が、除霊師の作る焼き肉とはね、想像もしなかったよ」
葛城小百合は除霊師だ。巷にあふれるニセモノではない。希少な本物の除霊師である。そんな小百合の除霊方法は単純明快。幽霊を憑依させ、彼らの望みを叶えさせて除霊する。
望みについても至極単純。幽霊たちが食べたかったもの、未練を残したものを一緒に食べる。『食べて除霊』が小百合の得意技。
今日もまた小百合は迷える幽霊を体に閉じ込めて、彼の思い残した食事に向かい合ったところである。
「換気しろよ、部屋中べっとり甘い匂いが染み付いてやがる」
……と、小百合の足元でぶつぶつと声が響いた。台所の床でくるりと丸くなっている黒い影がある。
「ケンタ、お仕事中だよ。口出し禁止」
「何が仕事だ。また無料奉仕しやがって」
そう吐き捨てるのは黒い夜を背負うような毛皮を持つシェパード犬、ケンタ。
小百合の除霊のパートナー兼、同居人。この世界で小百合とだけなぜか会話が交わせる、そんな不思議も、すっかり慣れた。小百合は除霊師、不思議は小百合の日常だ。
「さて、お仕事しますか」
ケンタの言葉を無視して小百合はずっしり重いフライパンを掴む。そしてそれを机の上にどん、と置いた。
山田は娘三人と父親の4人暮らしと言っていた。きっと彼らもフライパンを皿代わりに食べたはず。
「……さあ、一緒に食べよう」
手を合わせ、熱々の肉と野菜を口に含むと、なぜか懐かしい味がした。火照った顔を抑えて小百合は幸せの息を漏らす。
「おいしいです。野菜の水分と、お肉と……甘辛い味。あー。白いご飯も欲しかったな」
小百合がそう呟いた瞬間、部屋の外から人の声が聞こえてきた。それはアパートの狭い廊下に反響し、まるで波の音のように広がる。窓から外を覗けば、廊下には黒の喪服を纏う人々が集まりつつあった。
雨が降り始めたのか、色とりどりの傘が揺れ、喪服の黒が余計に際立つ。
「……お通夜始まっちゃいましたね」
小百合は甘辛い肉を噛み締めながら、寂しく呟いた。
小百合の住むアパートの隣人、山田の部屋が急に騒がしくなったのは今朝のこと。気づけば葬儀会社の人間が出入りしはじめた。
ずっと入院ばかりを繰り返していた山田が亡くなったと知ったのは、昼過ぎ。
そして、亡くなったはずの山田が廊下に佇んでいたのは、茜色が差し込む夕暮れのこと。
寂しそうに立ち尽くす彼に、小百合は思わず声をかけていた。
未練を残して昇天できない彼を体に憑依させ、食べたいものを探り、料理を作ったときには、もうすっかり夜が更け、お隣では彼自身の通夜が始まってしまった。人々の悼みの声を聞きながら、その当人の未練を食べるのはなんとも不思議な感覚だった。
「素直に死ねばよかったのに、なんだって幽霊になったのかなあ、俺は」
山田も同じ気持ちなのだろう。ふてくされるように、不機嫌そうに吐き捨てる。
「未練があると人は死ねないんです。山田さんの未練がこの焼き肉ならいいんだけど」
「もっと遊びたかったし仕事もしたかった。未練は山盛りだ。何が俺の未練なのやら」
やがて廊下に女性の囁くような声が響いた。
もう一度窓から外を覗けば、喪服に身を包んだ女性が三人、肩を落として廊下を進み、隣の部屋の前に立ったところだ。彼女たちは弔問客に丁寧に頭を下げ、その沈んだ体を三人の男たちがそれぞれ優しく支えた。
「……娘なんて持つもんじゃないぞ。どうせ誰かのもんになる」
小百合の中の山田が寂しそうに悔しそうにつぶやいた……が、小さな影を見つけて彼の声が不意に止まる。
「お母さん」
女性の横にいた少女が、そう言って彼女の手を引っ張ったのだ。彼女は目を丸くして、きょろきょろと頭を動かす。
そして彼女の幼い目が小百合の家の窓をうっとりと見上げ、鼻を動かすのだ。
「……焼き肉食べたい。おじいちゃんの」
肉を噛み、野菜を噛む。一口ごとに山田の心が軽くなる。憑依させているとそれがよく分かる。そして小百合はその瞬間が好きだった。絡まった未練の解ける感触である。
「孫娘は野菜嫌いだったんだ。それが俺の焼き肉ですっかり解消だ。俺が死んだあとも、食ってくれればいいんだが」
「きっと、娘さんもお孫さんも、焼き肉といったらこれを思い出します、この先一生」
小百合の答えに山田は低く笑った。
「俺の未練は結局これか。すっかり俺もそのあたりの爺さんだなあ」
やがて小百合の体が軽くなる。彼は一粒の涙と、美味しい焼き肉の味だけを残して、小百合の中から静かに姿を消した。
「さようなら、山田さん」
フライパンから上がる湯気だけが、まるで彼の魂のようにゆらりと揺れて、換気扇の向こうに吸い込まれていった。
「全く馬鹿なお嬢さんだ」
小言が聞こえてきたのは深夜すぎ。外はまだ雨が降り続いているのか、湿気た空気の中に、焼き肉と線香の香りが広がっていた。
憑依のあとはいつも疲れて寝込んでしまう。そんな仕事後の余韻から揺り起こされると、目の前にはケンタが渋い顔で小百合を睨みつけていた。
「いつも余計なもん、抱え込みやがって」
その声は、心配性の山田と同じような響きがある。
「ケンタってお祖父ちゃんみたいだね」
「バカか。お前みたいな孫がいてたまるか」
文句を言うケンタを掴んで抱きしめ横になり、小百合はもう一度眠ろうと考える。
きっと目が覚めたら、雨は止む。朝も来る。山田が見送られる爽やかな朝の空気を想像して、小百合はそっと目を閉じた。
「一枚一枚ちんたら焼くんじゃないぞ。フライパンに切った山盛りの野菜と肉を入れてタレで煮るんだ。野菜から水分が出るだろ、そいつで薄まってちょうどよくなる」
山田の指示に従って、小百合が用意したのは大きなフライパンだ。熱したそこに、人参やキャベツ、もやし、そして牛肉。具で溢れそうなフライパンに注ぎ入れるのは甘めの焼き肉のタレ。油と野菜の水分がふつふつと湧き上がり部屋中に甘辛い香りが漂い始める。
「えっと。これって肉野菜炒め……?」
「焼き肉だよ、少なくとも俺の家では。ヤモメの作れる料理はこんなもんだ。この料理で娘を三人、立派に育てたんだ」
山田は自嘲気味にぼやく。
「俺だけなら肉だけでいいが、娘には野菜も食わさないといけないだろ」
小百合がフライパンに向き合っているのは、狭いアパートの一室、その台所。
振り返っても下を見てもどこにも小百合以外、人間の影はない。しわがれた声は、小百合の中から響いている。
「最期に食う飯が、除霊師の作る焼き肉とはね、想像もしなかったよ」
葛城小百合は除霊師だ。巷にあふれるニセモノではない。希少な本物の除霊師である。そんな小百合の除霊方法は単純明快。幽霊を憑依させ、彼らの望みを叶えさせて除霊する。
望みについても至極単純。幽霊たちが食べたかったもの、未練を残したものを一緒に食べる。『食べて除霊』が小百合の得意技。
今日もまた小百合は迷える幽霊を体に閉じ込めて、彼の思い残した食事に向かい合ったところである。
「換気しろよ、部屋中べっとり甘い匂いが染み付いてやがる」
……と、小百合の足元でぶつぶつと声が響いた。台所の床でくるりと丸くなっている黒い影がある。
「ケンタ、お仕事中だよ。口出し禁止」
「何が仕事だ。また無料奉仕しやがって」
そう吐き捨てるのは黒い夜を背負うような毛皮を持つシェパード犬、ケンタ。
小百合の除霊のパートナー兼、同居人。この世界で小百合とだけなぜか会話が交わせる、そんな不思議も、すっかり慣れた。小百合は除霊師、不思議は小百合の日常だ。
「さて、お仕事しますか」
ケンタの言葉を無視して小百合はずっしり重いフライパンを掴む。そしてそれを机の上にどん、と置いた。
山田は娘三人と父親の4人暮らしと言っていた。きっと彼らもフライパンを皿代わりに食べたはず。
「……さあ、一緒に食べよう」
手を合わせ、熱々の肉と野菜を口に含むと、なぜか懐かしい味がした。火照った顔を抑えて小百合は幸せの息を漏らす。
「おいしいです。野菜の水分と、お肉と……甘辛い味。あー。白いご飯も欲しかったな」
小百合がそう呟いた瞬間、部屋の外から人の声が聞こえてきた。それはアパートの狭い廊下に反響し、まるで波の音のように広がる。窓から外を覗けば、廊下には黒の喪服を纏う人々が集まりつつあった。
雨が降り始めたのか、色とりどりの傘が揺れ、喪服の黒が余計に際立つ。
「……お通夜始まっちゃいましたね」
小百合は甘辛い肉を噛み締めながら、寂しく呟いた。
小百合の住むアパートの隣人、山田の部屋が急に騒がしくなったのは今朝のこと。気づけば葬儀会社の人間が出入りしはじめた。
ずっと入院ばかりを繰り返していた山田が亡くなったと知ったのは、昼過ぎ。
そして、亡くなったはずの山田が廊下に佇んでいたのは、茜色が差し込む夕暮れのこと。
寂しそうに立ち尽くす彼に、小百合は思わず声をかけていた。
未練を残して昇天できない彼を体に憑依させ、食べたいものを探り、料理を作ったときには、もうすっかり夜が更け、お隣では彼自身の通夜が始まってしまった。人々の悼みの声を聞きながら、その当人の未練を食べるのはなんとも不思議な感覚だった。
「素直に死ねばよかったのに、なんだって幽霊になったのかなあ、俺は」
山田も同じ気持ちなのだろう。ふてくされるように、不機嫌そうに吐き捨てる。
「未練があると人は死ねないんです。山田さんの未練がこの焼き肉ならいいんだけど」
「もっと遊びたかったし仕事もしたかった。未練は山盛りだ。何が俺の未練なのやら」
やがて廊下に女性の囁くような声が響いた。
もう一度窓から外を覗けば、喪服に身を包んだ女性が三人、肩を落として廊下を進み、隣の部屋の前に立ったところだ。彼女たちは弔問客に丁寧に頭を下げ、その沈んだ体を三人の男たちがそれぞれ優しく支えた。
「……娘なんて持つもんじゃないぞ。どうせ誰かのもんになる」
小百合の中の山田が寂しそうに悔しそうにつぶやいた……が、小さな影を見つけて彼の声が不意に止まる。
「お母さん」
女性の横にいた少女が、そう言って彼女の手を引っ張ったのだ。彼女は目を丸くして、きょろきょろと頭を動かす。
そして彼女の幼い目が小百合の家の窓をうっとりと見上げ、鼻を動かすのだ。
「……焼き肉食べたい。おじいちゃんの」
肉を噛み、野菜を噛む。一口ごとに山田の心が軽くなる。憑依させているとそれがよく分かる。そして小百合はその瞬間が好きだった。絡まった未練の解ける感触である。
「孫娘は野菜嫌いだったんだ。それが俺の焼き肉ですっかり解消だ。俺が死んだあとも、食ってくれればいいんだが」
「きっと、娘さんもお孫さんも、焼き肉といったらこれを思い出します、この先一生」
小百合の答えに山田は低く笑った。
「俺の未練は結局これか。すっかり俺もそのあたりの爺さんだなあ」
やがて小百合の体が軽くなる。彼は一粒の涙と、美味しい焼き肉の味だけを残して、小百合の中から静かに姿を消した。
「さようなら、山田さん」
フライパンから上がる湯気だけが、まるで彼の魂のようにゆらりと揺れて、換気扇の向こうに吸い込まれていった。
「全く馬鹿なお嬢さんだ」
小言が聞こえてきたのは深夜すぎ。外はまだ雨が降り続いているのか、湿気た空気の中に、焼き肉と線香の香りが広がっていた。
憑依のあとはいつも疲れて寝込んでしまう。そんな仕事後の余韻から揺り起こされると、目の前にはケンタが渋い顔で小百合を睨みつけていた。
「いつも余計なもん、抱え込みやがって」
その声は、心配性の山田と同じような響きがある。
「ケンタってお祖父ちゃんみたいだね」
「バカか。お前みたいな孫がいてたまるか」
文句を言うケンタを掴んで抱きしめ横になり、小百合はもう一度眠ろうと考える。
きっと目が覚めたら、雨は止む。朝も来る。山田が見送られる爽やかな朝の空気を想像して、小百合はそっと目を閉じた。

彼女は食べて除霊する
- 著:みお
- イラスト:syo5
- 発売日:2021年8月20日
- 価格:770円(本体700円+税10%)
書店でのご予約はこちらの予約票をご利用ください