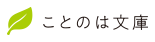月明かり、神様といなり寿司
食べたい。と、思ってしまえば堪らない。食べたくて、食べたくて仕方がない。その現象を『神様が降りてきた』というのだ……と、小百合はご近所のお婆さんにそう習った。
「いなり寿司が、食べたい!」
「真夜中に騒ぐな」
布団を蹴飛ばして叫べば、小百合の真横の黒い塊が頭も上げすにそう言った。
「私達の職業は夜が営業時間だって、ケンタそう言ってたじゃない」
「仕事ならな」
渋々顔を上げたのは巨体のシェパード犬だ。彼は不機嫌そうに吐き捨てる。
「でもな、お嬢さん。今は除霊中か?」
小百合の職業は『除霊師』である。それも世界的に希少価値の高い、本物の。
小百合の仕事のやり方は、至極かんたん。幽霊を体に憑依させ、幽霊が『未練』を残す食べ物を食べて除霊する。
少々珍しい職業ではあるものの、普通の仕事と変わらないこともある。つまり、仕事中毒になると私生活とのバランスを取るのが難しい、ということだ。
幽霊の望みのまま彼らの思い残しを一緒に食べる。そんな誇り高い仕事だが、最近はプライベートをおざなりにしすぎた。
「だって、最近仕事ばっかりで自分の好きなものを食べてなかったでしょ?」
口の中に広がるのは甘い薄揚げ、少しだけ熱を持ったふわふわの甘酸っぱい酢飯。想像するともう我慢ができない。
「あれ作りたいな。関西風のいなり寿司!」
小百合は台所に滑り込み、行平鍋にたっぷりのお湯を沸かす。冷凍庫から冷凍のご飯を放り出し、寿司の具材を切り刻み、薄揚げを冷蔵庫から引っ張り出す。
「もう丑三つ時だぞ、朝まで我慢しろ」
「私が食べたいもの我慢できると思う?」
小百合の足元をうろつくシェパード犬は、除霊の相棒……かつては人間だったと主張するケンタ。小百合とだけ会話を交わせるという、そんな不思議にもすっかり慣れた。
外は月が大きく浮かび、蕩けて落ちてきそうな夜である。その満月の光の下をぞろぞろと怪しげな影が揺れる、生きたものとは異なる息吹が行き交う。小百合の住むここ、波岸町は幽霊と怪異が名物だ。除霊師が犬と会話できるくらい、不思議でも何でもない。
「前の道で工事してるし、ちょっとくらい音を立てたって大丈夫だよ」
小百合はベランダのカーテンを薄く開けて、外を見る。アパート前の道路では深夜前からなにかの工事が始まった。
深夜に工事をすると昨日報告を受けていた。その予告通り、前の道からは未明頃からカタカタと低い音が響いている。その音に紛れ込ませるように小百合は調理を続けた。
「関西風は確か、具沢山で揚げは薄味」
あっさり薄味で仕上げた薄揚げは三角になるように切って、破れないように気をつけながら真ん中から割く。中の酢飯は具沢山が関西風だ。こってり甘辛く煮込んだしいたけ、人参、ゴボウを混ぜ込み……。
「余ってるハムとコーンも入れちゃおう」
小百合は歌うようにそう言って、好きなものを酢飯に混ぜる。
関西の”お稲荷さん”は好きなものを詰めたらいいのだ。ただ揚げは美しい黄金色になるように薄めに仕上げる。なぜならいなり寿司は狐の神様に供えるものだから。小百合は関西生まれのご近所さんにそう習った。
完成した酢飯を稲荷の耳の端までぎっしり詰める。指先にしみるのは、甘い汁と酢飯の爽やかな香り。
「こんな夜中にいなり寿司ね……」
鼻のいいケンタは鼻を布団に押し付けて抗議する。しかし小百合は気にせず、できたばかりのいなり寿司を皿に並べた。
「関東風は米俵に見立てて俵型だけど、関西風は狐の耳の三角形なんだって」
白い皿の上、淡い黄色の三角帽子が並ぶ様子はなるほど、狐の耳に見えた。
「いっただっきまーす」
食べたくて仕方のない状況を『神様が降りてきた』なら、きっとこの衝動は『稲荷の神様が降りてきた』だ。
小百合は手を合わせ、いなり寿司を噛みしめる。具沢山の米に染み込んだ、じゅわりと甘い味。甘さとは旨さだ。いつか誰かから聞いたそんな言葉を思い出しながら無我夢中に1つ、2つ。噛み締めて目を細めた途端、玄関のチャイムがびい、と低い音をたてた。
恐る恐る扉を開ければ、そこには青く煙る夜の闇と月明かり……そして。
「お騒がせしました。工事終わりました」
黄金の破片が散らばるような月明かりの下、玄関の向こうに立っていたのは若い男だった。
泥まみれの作業着の隣には、同じく泥まみれの工事道具が並んでいる。そして土で汚れた腕には灰色の狐像が抱かれていた。
それは神社の入り口でよく目にする、狛犬……ならぬ狛狐。小さいが艶めかしい狛狐は小百合と目があい、にこりと微笑んだ……そんな気がする。
小百合はいなり寿司を掴んだまま、ぽかんと彼を見つめる。
「……狐の像?」
「このアパートの前に古い稲荷社がありまして。今日の満月の日が、ちょうど神様の移動の日だったのです」
男の言葉は関西訛り。目を細めてニコリと微笑む。彼は小百合が掴んだままのいなり寿司を見つめると、その喉がこくん、と動いた。
途端、小百合の中からいなり寿司への欲求が音を立てて消えていく。
「……え?」
「どうも、ごちそうさんでした」
男は作業帽をひょいっととってペコリと頭を下げる……帽子の下にはぴょこんと飛び出た二つの大きな耳。弧を描くようなその細い瞳は、腕に抱かれた彫像にそっくりだった。
窓の外を見ても、そこに工事の形跡はなく、
残されたのは三角のいなり寿司だけ。
小百合は机に顎を乗せたまま、綺麗に並ぶいなり寿司をぼんやり見つめる。
体の奥底に残る暖かさと、ほんの少しの寂しさは、除霊のあとと同じ感覚だ。
つまり、小百合は神様を飲み込んだ……いや、神様が小百合の体を借りに来たのか。
あれほど燃えたぎっていたいなり寿司への欲求は、消え失せた。きっと神様が持って消えてしまったのだ。
「結局お仕事になっちゃったね、ケンタ」
稲荷の神様は食の神様だと言われることもあるらしい。ならば小百合にきっとぴったりの神様なのだろう。
「いなり寿司は神様のお供え物、かあ」
「お前! 無事だったからいいものを」
ケンタは耳を伏せてぎゃんと吠えるが小百合は気にもならない。
神様だって、供えられるいなり寿司を見ているだけではつまらない。ときには食べて味わいたい……『食べたい』はきっと、有史以来すべての生き物の自然な欲求だ。
「気に入ってくれたかな、ハムとコーン入りのいなり寿司」
部屋に残る甘い香りを吸い込んで、小百合は目を閉じ、両手を広げて布団に転がる。ケンタはすっかり呆れ顔で小百合の隣でくるりと丸くなる。きっと、今夜は稲荷詣での夢を見るに違いない。
「いなり寿司が、食べたい!」
「真夜中に騒ぐな」
布団を蹴飛ばして叫べば、小百合の真横の黒い塊が頭も上げすにそう言った。
「私達の職業は夜が営業時間だって、ケンタそう言ってたじゃない」
「仕事ならな」
渋々顔を上げたのは巨体のシェパード犬だ。彼は不機嫌そうに吐き捨てる。
「でもな、お嬢さん。今は除霊中か?」
小百合の職業は『除霊師』である。それも世界的に希少価値の高い、本物の。
小百合の仕事のやり方は、至極かんたん。幽霊を体に憑依させ、幽霊が『未練』を残す食べ物を食べて除霊する。
少々珍しい職業ではあるものの、普通の仕事と変わらないこともある。つまり、仕事中毒になると私生活とのバランスを取るのが難しい、ということだ。
幽霊の望みのまま彼らの思い残しを一緒に食べる。そんな誇り高い仕事だが、最近はプライベートをおざなりにしすぎた。
「だって、最近仕事ばっかりで自分の好きなものを食べてなかったでしょ?」
口の中に広がるのは甘い薄揚げ、少しだけ熱を持ったふわふわの甘酸っぱい酢飯。想像するともう我慢ができない。
「あれ作りたいな。関西風のいなり寿司!」
小百合は台所に滑り込み、行平鍋にたっぷりのお湯を沸かす。冷凍庫から冷凍のご飯を放り出し、寿司の具材を切り刻み、薄揚げを冷蔵庫から引っ張り出す。
「もう丑三つ時だぞ、朝まで我慢しろ」
「私が食べたいもの我慢できると思う?」
小百合の足元をうろつくシェパード犬は、除霊の相棒……かつては人間だったと主張するケンタ。小百合とだけ会話を交わせるという、そんな不思議にもすっかり慣れた。
外は月が大きく浮かび、蕩けて落ちてきそうな夜である。その満月の光の下をぞろぞろと怪しげな影が揺れる、生きたものとは異なる息吹が行き交う。小百合の住むここ、波岸町は幽霊と怪異が名物だ。除霊師が犬と会話できるくらい、不思議でも何でもない。
「前の道で工事してるし、ちょっとくらい音を立てたって大丈夫だよ」
小百合はベランダのカーテンを薄く開けて、外を見る。アパート前の道路では深夜前からなにかの工事が始まった。
深夜に工事をすると昨日報告を受けていた。その予告通り、前の道からは未明頃からカタカタと低い音が響いている。その音に紛れ込ませるように小百合は調理を続けた。
「関西風は確か、具沢山で揚げは薄味」
あっさり薄味で仕上げた薄揚げは三角になるように切って、破れないように気をつけながら真ん中から割く。中の酢飯は具沢山が関西風だ。こってり甘辛く煮込んだしいたけ、人参、ゴボウを混ぜ込み……。
「余ってるハムとコーンも入れちゃおう」
小百合は歌うようにそう言って、好きなものを酢飯に混ぜる。
関西の”お稲荷さん”は好きなものを詰めたらいいのだ。ただ揚げは美しい黄金色になるように薄めに仕上げる。なぜならいなり寿司は狐の神様に供えるものだから。小百合は関西生まれのご近所さんにそう習った。
完成した酢飯を稲荷の耳の端までぎっしり詰める。指先にしみるのは、甘い汁と酢飯の爽やかな香り。
「こんな夜中にいなり寿司ね……」
鼻のいいケンタは鼻を布団に押し付けて抗議する。しかし小百合は気にせず、できたばかりのいなり寿司を皿に並べた。
「関東風は米俵に見立てて俵型だけど、関西風は狐の耳の三角形なんだって」
白い皿の上、淡い黄色の三角帽子が並ぶ様子はなるほど、狐の耳に見えた。
「いっただっきまーす」
食べたくて仕方のない状況を『神様が降りてきた』なら、きっとこの衝動は『稲荷の神様が降りてきた』だ。
小百合は手を合わせ、いなり寿司を噛みしめる。具沢山の米に染み込んだ、じゅわりと甘い味。甘さとは旨さだ。いつか誰かから聞いたそんな言葉を思い出しながら無我夢中に1つ、2つ。噛み締めて目を細めた途端、玄関のチャイムがびい、と低い音をたてた。
恐る恐る扉を開ければ、そこには青く煙る夜の闇と月明かり……そして。
「お騒がせしました。工事終わりました」
黄金の破片が散らばるような月明かりの下、玄関の向こうに立っていたのは若い男だった。
泥まみれの作業着の隣には、同じく泥まみれの工事道具が並んでいる。そして土で汚れた腕には灰色の狐像が抱かれていた。
それは神社の入り口でよく目にする、狛犬……ならぬ狛狐。小さいが艶めかしい狛狐は小百合と目があい、にこりと微笑んだ……そんな気がする。
小百合はいなり寿司を掴んだまま、ぽかんと彼を見つめる。
「……狐の像?」
「このアパートの前に古い稲荷社がありまして。今日の満月の日が、ちょうど神様の移動の日だったのです」
男の言葉は関西訛り。目を細めてニコリと微笑む。彼は小百合が掴んだままのいなり寿司を見つめると、その喉がこくん、と動いた。
途端、小百合の中からいなり寿司への欲求が音を立てて消えていく。
「……え?」
「どうも、ごちそうさんでした」
男は作業帽をひょいっととってペコリと頭を下げる……帽子の下にはぴょこんと飛び出た二つの大きな耳。弧を描くようなその細い瞳は、腕に抱かれた彫像にそっくりだった。
窓の外を見ても、そこに工事の形跡はなく、
残されたのは三角のいなり寿司だけ。
小百合は机に顎を乗せたまま、綺麗に並ぶいなり寿司をぼんやり見つめる。
体の奥底に残る暖かさと、ほんの少しの寂しさは、除霊のあとと同じ感覚だ。
つまり、小百合は神様を飲み込んだ……いや、神様が小百合の体を借りに来たのか。
あれほど燃えたぎっていたいなり寿司への欲求は、消え失せた。きっと神様が持って消えてしまったのだ。
「結局お仕事になっちゃったね、ケンタ」
稲荷の神様は食の神様だと言われることもあるらしい。ならば小百合にきっとぴったりの神様なのだろう。
「いなり寿司は神様のお供え物、かあ」
「お前! 無事だったからいいものを」
ケンタは耳を伏せてぎゃんと吠えるが小百合は気にもならない。
神様だって、供えられるいなり寿司を見ているだけではつまらない。ときには食べて味わいたい……『食べたい』はきっと、有史以来すべての生き物の自然な欲求だ。
「気に入ってくれたかな、ハムとコーン入りのいなり寿司」
部屋に残る甘い香りを吸い込んで、小百合は目を閉じ、両手を広げて布団に転がる。ケンタはすっかり呆れ顔で小百合の隣でくるりと丸くなる。きっと、今夜は稲荷詣での夢を見るに違いない。

彼女は食べて除霊する
- 著:みお
- イラスト:syo5
- 発売日:2021年8月20日
- 価格:770円(本体700円+税10%)
書店でのご予約はこちらの予約票をご利用ください