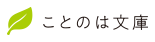「嵐の行方」
末広さんの淹れてくれる緑茶は、いつもとろりと濁っている。茶筒のふたでざっくりと量った茶葉を惜しみなく急須へ入れてお湯を注ぎ、茶碗に注いだお茶をもう一度急須に戻すので、特濃のお茶ができあがる。
茶碗の底が見えないほど濃いお茶は、爽やかな香りの中にはっきりと茶葉の甘みが感じられて、とても美味しい。
九月に入り、まだ残暑が厳しい。冷房で冷えた身体を美味しいお茶で温めながら、『なごみ典礼』清澄会館のパントリーで末広さんの推理に私は耳を傾けている。
「つまり、人間には無理や。ガルター・ポイスト現象やと、あたしは思う」
口元を引き結び、大真面目で断言する末広さんを、私が訂正する。
「ポルター・ガイスト、ですね」
確か、ドイツ語で『騒がしい幽霊』という意味だ。
「私は、誰か人間がやってると思うんだけど」
藤原さんが、コンビニのビニール袋を丁寧に三角に畳みながら、口を尖らせた。
私たちが論じているのは、ここ数日、会館のなかで続いている奇妙な出来事の真相だ。告別式のあと、お客様を火葬場へ送り出し、初七日と精進落としのセッティングが終わると、あとはお帰りを待つのみとなる。昼食を食べ終え、持ち寄ったデザートを分け合って食べてもまた時間が余る、というときは、お茶とおしゃべりに花が咲く。
奇妙な出来事、というのは、末広さんのいうように、ポルター・ガイストが中心だ。何せ、しめやかに行われるべきお葬儀の現場で、大きな物音が立て続けに三件も起こっている。
「ええと、最初は九月九日ですね。お式の最中に、倉庫の段ボールが崩れて大雪崩。翌日、きちんと積み直したのに、また同じ段ボールが崩れた。どちらも、お経の始まった直後っていうのが怖いですよね。その次の日、つまり昨日は昼間、式場の準備中に間接照明の板が割れて天井から降ってきた」
私が順番に思い出す。
「せや。それらが全部、八日以降に起こってるんや。八日の夜といえば、なごみ典礼始まって以来のご依頼殺到日や」
八日は大型の台風十号が千葉県に大きな被害をもたらして、交通機関にも大きな影響が出た。そんな嵐の夜に、立て続けにあちこちの病院から連絡が入り、雨の中、夜勤のスタッフは一睡もせずに出動とご遺体の安置を繰り返すことになった。
「結局、なごみ典礼の会館でお預かりできない方は、同業者にお願いしたんですよね」
私はよく磨かれたパントリーの床に視線を落とす。多くの方がそれぞれの病院で同時に亡くなったのは偶然だろうけれど、悲しいことが重なったと思うと気持ちはしゅんと沈む。
「そうよ。うちを信頼してご連絡をくれたお客様に普段なら絶対にそんなことはしないけれど、あの日は保冷庫が満室になってしまったから……蒸し暑い夜だったし仕方なかったわね。紹介先がライバルの『大江戸葬祭』ってところが悔しいけど」
お茶碗を片手に、藤原さんが頬杖をつく。末広さんは顎の下に手を当てて、推理の続きを披露する。
「八日に亡くなったご遺体の誰かが、この世に残した未練を伝えたいんやと思う」
「まだお葬儀をあげられていないのは……お二人いらっしゃるんでしたっけ」
一人は風邪をこじらせて肺炎で亡くなった九十代の男性。もうひとりはアレルギー発作で呼吸困難になった四十代の女性だ。
「未練があるとしたら、女性の方ですよね」
私のコメントに、藤原さんが首を振る。
「どっちも未練があるに決まってるじゃないの。高齢者だって、自分が急に死ぬなんて思ってないわよ、今どき」
「じゃあ、二人の霊がそれぞれ主張している、というのはどうでしょう」
「二人も霊がおったら敵わんなあ」
末広さんが天井を仰いだのと同時に、内線が鳴った。私が電話を取ると、事務所の権藤さんから御葬家が火葬場を出発したというご連絡だった。
のんびりしていた空気が、ぱっと仕事モードに切り替わる。末広さんを手伝い、精進落としのお膳に、お寿司と、温かい汁物を並べる。初七日法要のための焼香炉に炭を点け、空調も整えなければならない。
慌ただしく準備をして、お迎えのために一階へ降りる。霊安室へのお参りの方だろう、エレベーター前のベンチに、黒い服を纏った男性がひとり座っていたので、そっと目礼をした。
「まだ直ってないのよね」
藤原さんが、自動ドアを手で押し開ける。自動ドアは、台風の日にセンサーが壊れてしまい、それ以降手動で開け閉めをしなくてはいけない。館内は冷房を強めにかけているので、隙間なく閉めておくように、権藤館長からお達しが出ている。お手水の桶の準備を済ませると、私は駐車場係の小鷹さんが見当たらないので会館の裏手にある喫煙所へ探しにいった。
「小鷹さーん、まもなくお客様のお戻りですよ」
お客様がいない時間帯、ふらっと煙草を吸いに行ってしまう小鷹さんは、東北訛りの穏やかなおじいさんだ。
「おう、連絡きたの。じゃあ仕事しないとね」
にこにこと悪びれもせず、道路の先が見える位置に移動した。
「お疲れ様です。遅くなってすみません」
伊織さんが事務所から降りてきて、私たちに声をかけた。私たちはお昼の休憩をいただいたけれど、伊織さんは今まで別の御葬家へお花を届けに出掛けていた。暑さのなか、分刻みの移動をこなしたはずなのに、いつもながらの凛とした佇まいだ。
みんなで外で待っていると全員が汗だくになってしまうので、お客様の車列が見えたら、小鷹さんが館内の私たちに知らせてくれる手筈になっている。
「お帰りでーす」
ほどなく小鷹さんが表から声を掛けてくれた。私たちはドアを開け放ち、玄関前でお客様をお迎えする。伊織さんの素早く流れるような動きに見とれながら、私もお客様がスムーズに移動できるよう気を配る。
「お水をお持ちしましょうか」
藤原さんが、顔色の悪い女性に駆け寄る。初七日法要の前は、お客様の疲れも出てくるので、体調の悪そうな方がいないか観察するのも大事な仕事だ。女性は控室で少し休むことになり、藤原さんがお部屋まで付き添う。昨夜から、くしゃみを繰り返す人もいたので、親族内で風邪をもらってしまったのかもしれない。
数分後、女性を除く全員が着席すると、初七日法要が始まった。
僧侶が木魚をリズミカルに叩く。御葬家の方は、移動の繰り返しで疲れたのか、うとうととする人もちらほら出てきた。
僧侶の合図で、藤原さんがお盆に載った焼香炉を取りに行き、回し焼香が始まる。
初七日法要は時間が短いので、左右両側から一基ずつ回す。私はタイミングを見て、残りの一基をお客様の手元に運ぼうとした。
その時だった。
祭壇の上に飾られたお花の陰から黒い靄のようなものが一瞬見え、六灯籠(ろくとうろう)の右片方がゆっくりと倒れてきた。
幸い祭壇の上から落ちることはなかったが、カターン、と音が鳴って、僧侶のお読経が一呼吸分だけ止まった。
伊織さんが音もなく僧侶の脇へ進み出て一礼し、長身を活かして素早く六灯籠を起こす。伊織さんが戻ってくると、式場内は何事もなかったかのように回し焼香が進んだ。気まずい空気は残ったものの、僧侶の法話も終わり、お清め室で精進落としのお席へと場は移った。
「先程は、大変失礼いたしました」
私と藤岡さんが配膳スタッフを手伝って、献杯のお飲み物をご用意する間に、伊織さんがお詫びをする。僧侶と喪主様は向かい合って祭壇の前に座っていたので、お二人に同時に謝る形となった。私は「伊織さんがんばれ」と心の中で祈りながら、横目で事の成り行きを見守る。
僧侶は苦笑いを浮かべつつも、品よく片手を顔の前で振った。
「いえいえ。驚きましたが……地震などでなくてよかったです」
一方、喪主様は渋面で伊織さんの顔を振り仰いだ。
「本当に、ご僧侶にお怪我がなくてよかったですが……安全確認はきちんとされているんですよね?」
喪主様は江東区内の病院で長く看護婦長を務めていた女性で、今は退職している。白髪をきりりとしたショートカットにまとめ、紫の色付きメガネをかけていた。
「勿論でございます。通常はあのようなことは無いのですが……誠に申し訳ございませんでした」
伊織さんが深々と礼をするのに対し、喪主様は口を引き結ぶ。
「済んだことなので、もう結構。それより食事を始めてください」
これってクレームになってしまった、ということだろうか。ハラハラしながら献杯のあと、式場の片付けに向かう。
椅子や焼香炉の片付けをしつつ、紺色のカーテンで仕切られた祭壇の裏手に回り、六灯籠が落ちた原因を藤原さんと調べてみる。
階段を裏側から見るような格好で、蛍光灯が取り付けられた祭壇の内側が見えて明るい。白木の祭壇は横板や屋根は重いけれど、他のパーツは女性でも軽々と持ち上げられる。六灯籠は、下から二段目に載っている。その名の通り、左右片方に三つずつ明かりが灯り、故人の輪廻転生の道筋を照らす役割をしているそうだ。三つ横並びのため、横揺れには強いけれど、前後に力がかかると倒れる可能性はある。
とはいえ、わざと後ろから押したりしない限り、式中に前へ倒れてきたりはしない。
「私は焼香炉をお客様から受け取る瞬間だったから、倒れたところは見てないのよね」
藤原さんが、腕組みをしたまま、上下左右から六灯籠を眺める。
「コードは結構長いんですね」
灯籠や透かし彫りの飾りに付いているライトは、裏側に電源コードが垂らされていて、祭壇の裏で電源タップにつながれている。祭壇と一番奥の壁の間には、使われていないパーツがパズルを組み合わせるように収納されている。
「そうね……うっく……ちゅん!」
藤原さんが両手で口元を多い、控えめで可憐なくしゃみをした。
「くしゃみ、可愛いですね」
私がつい言及すると、藤原さんは照れ隠しのようにハンカチでローズピンクの唇を押さえる。
「埃っぽいのよ、ここのカーテン。古すぎて……でも埃だけじゃなくて、何か匂いがしない?」
祭壇の真上には、換気口がある。顔を向けてみたが、そこから匂っているわけではないようだ。
「ちょっと私には分かりません」
私は首を捻るばかりだが、藤原さんは形のよい鼻をうごめかす。
「台風の日から時々、異臭の報告を受けているの。ほら、壁の隙間に雨水が漏ってカビが生えたりするでしょう。清澄会館も、建ててから結構経つから」
傷や汚れは目に見える箇所を修復すればよいけれど、匂いとなると対処が難しそうだ。
「お疲れ様です」
カーテン越しに、伊織さんの声が聞こえたかと思うと、伊織さんも祭壇の裏側にやってきた。
「伊織くん、遅かったわね。すぐ調べに来るかと思ったのに」
藤原さんの苦言に対し、伊織さんが苦笑した。
「お待たせしてすみません。実は、献杯のあと、陰膳のお寿司が一貫足りないことに末広さんが気付きまして」
『一貫足りない?』
私と藤原さんの声が重なった。陰膳とは、故人にお供えする分のお膳のことだ。
「足りないなんて、あり得ないわ。お料理が厨房から届き次第、確認しているもの」
藤原さんが断言する。私もうんうん、と横で頷く。お寿司は、大トロ・エンガワ・海老・サーモンの四貫一皿で、どれが欠けてもかなり目立つ。到着時のチェックで見落としたとしても、お供えする際に必ず気づくだろう。
「献杯のお供えで末広さんが気付いて、急ぎ厨房に連絡しました。お客様に気づかれないよう揃ったお皿と差し替え、足りない方を確認したのですが、確かにサーモンだけが無くなっていました」
伊織さんが、声を低くし淡々と状況を説明してくれる。藤原さんはしばらく腕を組み、考えていたけれど、すぐに唸りながら頭を抱えた。
「ううん、難しいわね。スタッフが意図的に一貫抜いたなら、説明がつくけど……私と西宮さん、末広さんはずっと一緒にいたからそれも無いわ。初七日法要の間に、誰かが食べてしまったのかしら」
私は記憶を辿り、あっと叫んだ。
「お部屋で一名様お休みでしたよね。ご気分が悪いって仰っていた女性の方……ってことはない、ですよね」
伊織さんも藤原さんも、首を振る。親族控室からお清め室に行くには、式場の前を横切らなければいけない。さらに、お清め室とパントリーを末広さんが行き来しているため、こっそり忍び込んでもすぐに見つかってしまうだろう。
「一貫無くなったとしたら、スタッフが駐車場へお迎えに降りたタイミングしかありませんね」
伊織さんが表情を曇らせる。
「実は、このところ続いていたポルター・ガイスト現象について、私なりに調べていたのですが、その結論がサーモンの件で覆されてしまいました」
「え、結論って、原因がわかったんですか」
私が期待を込めて、伊織さんの顔を見つめる。
「ひとまず、表に出ましょうか」
伊織さんはカーテンを開いて、どうぞ、と私たちを先に祭壇裏から出してくれる。
「式場の真後ろは、壁を隔てて倉庫になっています。最初のポルター・ガイスト現象はお読経の開始と共に倉庫の段ボールが崩れる、というものでした。中身はお茶で、大きさの割に軽い箱でした。天井ギリギリまで積み上がっていたものが、突然崩れたと聞いています。
同じ日のうちに、段ボールは積み直したのに、翌日また同じタイミングで崩れました。さらに次の日……昨日のことですが、式場の間接照明の板が外れて落下。入り口から祭壇へ向かって右側……カーテンレールのギリギリ手前辺りですね」
伊織さんが、私たちが立っているほぼ真上、壁に取り付けられた間接照明を指し示す。式場の天井より少し低い位置、壁沿いにぐるりと白色の磨りガラス風のアクリルパネルが渡されて、暖色の光が壁と天井に反射するように設置されている。式場内がふわっと優しい雰囲気になる演出だ。
ぱっと見ただけでは分からないのだけど、実は板の間に継ぎ目があり、中のLEDライトを交換するときに、簡単に作業できるようになっている。
「落下したのは一枚だけ。式場で作業していたのは生花部の紫藤さんひとりでした。大きな音に驚いて、慌てて式場から飛び出し、スタッフのいるパントリーに駆け込んだと聞いています」
昨日のポルター・ガイストに遭遇したのは、紫藤さんだったんだ。いつも手際よくお花を飾っているけれど、突然大きな物音がしたら、驚いてしまうのも無理はない。
「生花部の部長からは、お祓いをした方がいいんじゃないかと言われましたが、私は霊現象ではないと思っています」
伊織さんの言葉に、藤原さんも大きく頷いて、賛成する。
「当り前よ。どの故人様も丁重にお送りしているもの。未練があるとしたって、なごみ典礼の倉庫や式場を気に入るわけがないでしょう」
「ポルター・ガイスト現象は、国内外で有名な事例が実際にあるので、完全に否定できるものではありません。ですが、なごみ典礼で起こっていることには、法則というか……共通点があります」
伊織さんが祭壇を振り返り、次に間接照明に視線を移した。
「もしかして……音ですか」
私が、頭の中でうっすら考えていた仮説を口にした。
倉庫の段ボール箱は、お読経が始まった直後に二回とも倒れている。
生花部の準備作業は、お花専用の台を組み立てるので、金属質の音が響くこともある。
そして、今日もお読経の最中に六灯籠が倒れた。
伊織さんの瞳は、静かに私を見つめ返したあと、そっと伏せられた。
「仰る通りです。音と人の気配があるときに、反応があります。しかし、音が犯人ではありません。これを見てください」
伊織さんは、カーテンの裾を持ち上げ、私たちに見せた。紺色に紛れてわかりにくいけれど、細かな黒い毛がくっついている。
「……うっくちゅん!」
藤原さんがまたくしゃみをした。
「人の髪の毛ではないですね。猫か犬でしょうか」
私が黒い毛をそっとつまんで観察する。長さ五㎝くらいで、先端が細い。
「猫よ、絶対! 私、犬はアレルギーないもの」
藤原さんが鼻声で叫んだ。そういえば、お通夜のときにくしゃみをしていた人も、もしかすると猫アレルギーがあったのかもしれない。
「猫が住み付いているってことですね」
私が観た祭壇の上の黒い靄は、猫の体の一部だったのかもしれない。私の問いかけに、伊織さんは頷いて応える。
「はい。恐らくかなり臆病で、体格の小さな猫が、自動ドアが壊れた頃に、入り込んでしまったのだと思います。倉庫の段ボール落下は、棚の最上段で猫はくつろいでいたところへお読経が始まり、驚いて段ボール箱に飛び移ったものの、バランスを崩して落下した、と考えられます。間接照明の件は、隙間にもぐりこんでいたけれど、生花部の台車に驚いて、その拍子に板を壊してしまったのではないでしょうか。しかし、お寿司のサーモンの件はお手上げです。猫がお刺身と酢飯をキレイに一貫分だけ、食べられるわけがありません」
つまり、一連のポルター・ガイスト現象の犯人は猫であることは確実らしい。
「お寿司の件は、人間という説が有力なのね。スタッフではないと思うわ。お客様の注文されたものに手をつけるなんて。お寿司一貫のためにクビになりたくないもの。ところで式場の中にまだ猫はいるのかしら」
藤原さんが辺りを見回す。私も椅子の下や、司会台の陰など猫が隠れていそうな場所に目をこらすが、何もいない。伊織さんが整った眉を下げて、苦笑する。
「いるはずですが、猫は繊細な生き物です。我々を警戒しているうちは、出てこないでしょうね。今夜もお通夜でこの式場を使う予定ですから、出てきてくれればいいのですが……」
怯えている小さな黒猫を思うと、早く見つけ出してあげたくなる。家に連れ帰ることは無理でも、しばらく清澄会館で預かって、保護猫団体などに依頼することはできるのではないか。
「単純だけど、餌でも置いておくしかないわね。猫はあとで誘い出すとして、お寿司泥棒はどうしたものかしら」
部外者が入り込んでいるのだとしたら少し怖い。伊織さんが、頷きながら口元を押さえた。
「そうですね……一般会葬の行き交うお通夜の時間ならいざ知らず、今の時間帯、式場付近に無関係な人間がいればかなり目立ちます。しかし、一階部分なら、話は別です」
一階は、会館を訪れる様々なお客様が、待合わせ場所などに使う。お葬儀の相談、霊安室へのお参り、葬儀後のご精算など、日中も人の出入りは多い。中には近所の方が、お手洗いだけ借りることもあるけれど、大抵は駐車場係の小鷹さんがご来館目的を確認し、事務所に連絡する。
「伊織くんの言うとおりね。小鷹さんに、一階の出入りについて内線で聞いてみるわ」
藤原さんが、式場に備え付けられた内線電話に駆け寄る。そういえば私と藤原さんがお客様のお迎えで一階に降りたとき、お待ち合わせ風の男性がいたような気がする。
「小鷹さん、お疲れ様。さっき、お迎えの前に一階で待ち合わせをしている人って誰かいた?」
藤原さんは小鷹さんと短いやりとりを交わし、受話器を置いた。
「やっぱり平服の男性が、ソファに座っていたそうよ。霊安室に安置されている方のお身内、と仰ったみたいだけど」
「その方が、いまどこにいるかが問題ですよね」
館内に潜んでいるなら、お通夜のお客様の安全も脅かしかねない。探しに行かなきゃ、と私が意気込んだとき、藤原さんが言葉を継いだ。
「それで……実はまだいるみたいなの、同じ人が。一階のソファに」
「ええっ」
つい声が裏返り、体をのけぞらせた。
「そんなに堂々としてるなんて」
逃げも隠れもせず、一階にいるという。伊織さんは落ち着いた声音で言った。
「一階の男性がお寿司泥棒と決まったわけではありません。降りてお話を伺ってみましょう」
伊織さんが先に立ち、私たちは階段を降りる。エレベーターホールのソファに座っていたのは、小鷹さんと同じくらいの年齢の男性だった。
胸元にイラストの描かれた黒いTシャツに、薄汚れたベージュのチノパンを履き、腰にデニムジャケットを巻きつけていた。顔は日焼けして、オーブンで焼いた七面鳥の皮のようにツヤがあり、少し乾いたような質感だ。白髪交じりの髪も髭も、最後に手入れしたのは随分前のように見受けられた。
「失礼いたします、お客様」
伊織さんが、穏やかに声を掛けた。すると、男性はこちらを見向きもせずにのそりと立ち上がり、左右に揺れながら歩き出す。具合が悪いのか、少し苦しげな様子で故障した自動ドアをこじ開けようとした。
「お待ちください」
伊織さんはすぐに追いつき、男性の後ろから自動ドアに手を掛ける。逃げられないように閉じ込めるのかと思いきや、伊織さんは片手にぐっと力を込めてドアを開けた。男性は、ハッとした顔つきで伊織さんを見上げる。『話を伺う』と言っていたのに、何故帰してしまうのだろう。藤原さんも、真剣な眼差しで事の成り行きを見守っている。恐らく、本当に伊織さんが男性を帰してしまいそうになったら、自分が引き留めるつもりでいるのだろう。
「どうぞ。ご不便をおかけして申し訳ありません」
残暑の熱気と湿気が流れ込むなか、男性は、無言で会釈をし、駐車場へ出て行こうとする。
藤原さんのピンヒールが、カツっと音を立てて前へ出た。伊織さんが男性の背中に声を掛ける。
「よろしければ、ご連絡いたしましょうか」
えっ、とその場の誰もが動きを止めた。私も何のことだろうと、伊織さんと男性から目が離せなくなる。
「お探しの猫が、見つかりましたらご連絡差し上げます」
ふわーっと熱い風が吹き込む中、伊織さんの声は駐車場に反響するほど明瞭に響いた。猫、というと、式場に隠れているというポルター・ガイストの犯人だろうか。男性はぎくりと体を強張らせ、こわごわ伊織さんを振り返った。
「差支えなければ、お名前とご連絡方法を、お教え願えますか」
男性の瞳に、初めてきらりと意志の光が見えた。乾いた唇が震え、良く通る声で答えが返ってくる。
「自分は……大鷺(おおさぎ)と言います。住所と電話番号はありません」
私と藤原さんは顔を見合わせた。住所も無い、ということはホームレスなのだろうか。そう言われると、汚れの目立つ服装は外で生活しているからだと分かる。
「申し訳ありませんが……勝手に館内にお入りいただくのは困ります」
藤原さんが言いながら表へ出ていく。優しい声音だったけれど、きっぱりと言い切る言葉は少し強い。大鷺、と名乗った男性は、一度何か言いかけたけれど、膝に手をつき、ぺこりと頭を下げた。
「……ごめんなさい」
「ああもう、謝らないでください。そうじゃなくて、猫を探したいなら、そう仰ってほしかったんです。というか、伊織くん、この人は猫の飼い主で間違いないの?」
藤原さんが、弱った、というように頬に手を当てて尋ねた。伊織さんは頷き、大鷺さんに向かって語りかける。
「藪から棒に失礼いたしました。お洋服に……ズボンの裾に、猫の毛が付いていたので」
大鷺さんがパッと自分の足元に視線を移す。
「大鷺様がいつから、一階にいたのかは分かりませんが、私たちが、御葬家のお迎えで一階に集まったのを見計らって、式場へ上がられたのですね。二階にスタッフがゼロとは限りませんが、ほとんど人目に付かないだろうと思われたのでしょう。実際に、御葬家が戻られるまで、式場は無人でしたから、猫を探しに忍び込んだのですね。お供えのお寿司が無くなったせいで、我々は騒いでいたのですが、お心当たりはございますか」
伊織さんの、穏やかな調子の問いかけを、大鷺さんの声が遮った。
「ご、ごめんなさい。本当は、ゴミ箱から拝借した刺身で呼び出そうとしたんですけど、ダメで……焦ってお供え物に手をつけてしまいました。あいつ、多分、もう何日も餌を食べてないから、弱っていると思って、それで……」
大鷺さんの告白に、私たちは顔を見合わせる。
「それでも、出てこなかったんですね」
私が呟くと、大鷺さんは頷いた。
「そうなんです、クロ助のやつ、出てこなくて……結局、自分で食べました。自分も台風の日に、雨風で寝床を失って、貯めてた金も流されてしまって……」
「台風の日、ですか。それは大変でしたね」
伊織さんが労わりの言葉をかけると、大鷺さんの顔が悲しそうに歪んだ。
「あの夜、暴風雨の中、避難所に向かおうと思ったんですけど、きっと他のひとたちに嫌がられると思ってやめたんです。そしたら、ここの駐車場が道路の向こう側から見えて、ずっと電気が付いてて明るかったので……少しだけ雨宿りさせてもらおうと思って、そこの小部屋に入らせてもらったんです」
男性が示した先には、小鷹さんが詰めている警備室があった。夜間は鍵を閉めて帰る決まりだけれど、たまたま忘れたのかもしれない。
「明け方、手洗いを借りたらその拍子にクロ助が中に入り込んでしまったんです。ごめんなさい。本当に……許してください」
大鷺さんは頭を下げて、私たちを拝んだ。
「どうする? 伊織くん。お寿司一貫で警察を呼ぶのも可哀想だしねえ」
藤原さんが、唇を尖らせる。うんうん、と私も大きく頷く。事情も事情出し、猫を見つけ次第、無罪放免でもいいのではないだろうか。伊織さんは、大鷺さんをじっと見つめてしばらく考えていたけれど、やがて口を開いた。
「まずは、猫を探すのを手伝っていただきましょう。そのあと、少しお話があります」
「ああ、ありがとうございます! 何も飲み食いしてないんです、あいつ」
大鷺さんは猫に会えることが嬉しかったらしく、ぱっと顔を輝かせた。
「私も手伝ってもいいですか」
藤原さんにそっと尋ねると、くすっと藤原さんが笑った。
「いいわよ。どうせもう仕事は終わりだもの。生花部がお花を飾りに来る前に、見つけ出してあげて」
あまり時間が無いので、早速、私と伊織さん、大鷺さんは式場に戻る。扉を開けると、祭壇の向こうでかさり、と何かが動く気配がした。
「クロ」
ちっちっち、と大鷺さんが舌を鳴らしながら猫を呼ぶ。ふと私は思いつき、パントリーからお椀にお吸い物の残りを入れて戻ってきた。ふわっと鰹出汁のよい香りが漂う。同時に、ひょこひょこと祭壇の後ろから壁沿いを小さな黒猫が歩いてきた。
「クロ助!」
子猫は飼い主に一瞥をくれると、お椀に駆け寄ってくんくんと匂いを嗅いだ。おつゆの温度はもう下がっているから、猫舌でも飲めるらしく、すぐに口をつけ、ぺろぺろと飲み始めた。満足げにゴロゴロと喉を鳴らし、美味しそうに目を細める。
「「かわいいですね」」
私と伊織さんの声が被り、二人で笑みを交わす。騒がしい幽霊ならぬ、お騒がせの黒猫は、しばらくすると舌なめずりをしながら飼い主に抱きかかえられた。
「では、私と大鷺さんは、館長を交えて話をしてきます。西宮さん、お疲れ様でした。また付き合わせてしまってすみませんでした」
伊織さんが、けほんと咳払いをする。館長を交えて、ということは、大鷺さんは警察に突き出すことはされないまでも、何らかの形で責任を負わされるんだろうか。
少し心配だったけれど、私が口を挟めることではない。
「ありがとうございました」
大鷺さんにもお礼を言われて、会釈で返す。お通夜の仕事もあるので、仕方なく式場を後にした。
それから、二週間が過ぎ、残暑も落ち着いてきた頃。なごみ典礼清澄会館は、新しい噂で持ちきりになっていた。末広さんが、緑茶に氷を放り込みながら、嬉しそうに語る。
「なんでも、前の仕事はデパートの駐車場係やったらしいで」
小鷹さんとともに働く駐車場係が一名増えたのだ。日焼けした精悍な顔が、往年の映画スターを思わせる、ということで、年配の女性スタッフの注目を集めている。
「まさに、権藤館長の大岡裁きっちゅうわけやな」
そう、新しいスタッフは、黒猫の飼い主だった大鷺さんだ。大鷺さんは権藤館長の采配で、正直に事情を話した人柄と経歴を認められ、晴れて駐車場係として採用された。家は社宅の一部屋をあてがわれたという。ペットは禁止なので便宜上、クロ助は保護猫団体に引き取られたが、社内で飼いたいという人がすでに現れたらしい。
「西宮さん、わかる? 大岡裁きって」
藤原さんに言われて、緑茶をいただきながら頷く。
「ええ、祖母が好きだったので」
エンディングテーマを口ずさむと、「それは遠山の金さん」と突っ込まれた。お奉行間違いだったらしい。火葬場からお客様が出発した、と連絡が入り、私たちは立ち上がって椅子を片づける。
表に出ると、外は雨が降り出しそうな曇り空だった。涼しい風が吹いて、もう秋だな、と分かる。新しい駐車場係は張り切って誘導灯を片手に、先輩について駐車場を行き来している。
「小鷹さん、大鷺さん、もうすぐお帰りです」
私たちが声を掛けると、二人は嬉しそうに振り返り、こちらへ走ってきた。先日は具合の悪そうだった大鷺さんは、よく食べて眠れているのか、軽快な動きに変わっている。
「一件落着ね」
「はい」
秋風に目を細めて、微笑む藤原さんの隣で、私は大きく頷いた。
(了)
末広さんの淹れてくれる緑茶は、いつもとろりと濁っている。茶筒のふたでざっくりと量った茶葉を惜しみなく急須へ入れてお湯を注ぎ、茶碗に注いだお茶をもう一度急須に戻すので、特濃のお茶ができあがる。
茶碗の底が見えないほど濃いお茶は、爽やかな香りの中にはっきりと茶葉の甘みが感じられて、とても美味しい。
九月に入り、まだ残暑が厳しい。冷房で冷えた身体を美味しいお茶で温めながら、『なごみ典礼』清澄会館のパントリーで末広さんの推理に私は耳を傾けている。
「つまり、人間には無理や。ガルター・ポイスト現象やと、あたしは思う」
口元を引き結び、大真面目で断言する末広さんを、私が訂正する。
「ポルター・ガイスト、ですね」
確か、ドイツ語で『騒がしい幽霊』という意味だ。
「私は、誰か人間がやってると思うんだけど」
藤原さんが、コンビニのビニール袋を丁寧に三角に畳みながら、口を尖らせた。
私たちが論じているのは、ここ数日、会館のなかで続いている奇妙な出来事の真相だ。告別式のあと、お客様を火葬場へ送り出し、初七日と精進落としのセッティングが終わると、あとはお帰りを待つのみとなる。昼食を食べ終え、持ち寄ったデザートを分け合って食べてもまた時間が余る、というときは、お茶とおしゃべりに花が咲く。
奇妙な出来事、というのは、末広さんのいうように、ポルター・ガイストが中心だ。何せ、しめやかに行われるべきお葬儀の現場で、大きな物音が立て続けに三件も起こっている。
「ええと、最初は九月九日ですね。お式の最中に、倉庫の段ボールが崩れて大雪崩。翌日、きちんと積み直したのに、また同じ段ボールが崩れた。どちらも、お経の始まった直後っていうのが怖いですよね。その次の日、つまり昨日は昼間、式場の準備中に間接照明の板が割れて天井から降ってきた」
私が順番に思い出す。
「せや。それらが全部、八日以降に起こってるんや。八日の夜といえば、なごみ典礼始まって以来のご依頼殺到日や」
八日は大型の台風十号が千葉県に大きな被害をもたらして、交通機関にも大きな影響が出た。そんな嵐の夜に、立て続けにあちこちの病院から連絡が入り、雨の中、夜勤のスタッフは一睡もせずに出動とご遺体の安置を繰り返すことになった。
「結局、なごみ典礼の会館でお預かりできない方は、同業者にお願いしたんですよね」
私はよく磨かれたパントリーの床に視線を落とす。多くの方がそれぞれの病院で同時に亡くなったのは偶然だろうけれど、悲しいことが重なったと思うと気持ちはしゅんと沈む。
「そうよ。うちを信頼してご連絡をくれたお客様に普段なら絶対にそんなことはしないけれど、あの日は保冷庫が満室になってしまったから……蒸し暑い夜だったし仕方なかったわね。紹介先がライバルの『大江戸葬祭』ってところが悔しいけど」
お茶碗を片手に、藤原さんが頬杖をつく。末広さんは顎の下に手を当てて、推理の続きを披露する。
「八日に亡くなったご遺体の誰かが、この世に残した未練を伝えたいんやと思う」
「まだお葬儀をあげられていないのは……お二人いらっしゃるんでしたっけ」
一人は風邪をこじらせて肺炎で亡くなった九十代の男性。もうひとりはアレルギー発作で呼吸困難になった四十代の女性だ。
「未練があるとしたら、女性の方ですよね」
私のコメントに、藤原さんが首を振る。
「どっちも未練があるに決まってるじゃないの。高齢者だって、自分が急に死ぬなんて思ってないわよ、今どき」
「じゃあ、二人の霊がそれぞれ主張している、というのはどうでしょう」
「二人も霊がおったら敵わんなあ」
末広さんが天井を仰いだのと同時に、内線が鳴った。私が電話を取ると、事務所の権藤さんから御葬家が火葬場を出発したというご連絡だった。
のんびりしていた空気が、ぱっと仕事モードに切り替わる。末広さんを手伝い、精進落としのお膳に、お寿司と、温かい汁物を並べる。初七日法要のための焼香炉に炭を点け、空調も整えなければならない。
慌ただしく準備をして、お迎えのために一階へ降りる。霊安室へのお参りの方だろう、エレベーター前のベンチに、黒い服を纏った男性がひとり座っていたので、そっと目礼をした。
「まだ直ってないのよね」
藤原さんが、自動ドアを手で押し開ける。自動ドアは、台風の日にセンサーが壊れてしまい、それ以降手動で開け閉めをしなくてはいけない。館内は冷房を強めにかけているので、隙間なく閉めておくように、権藤館長からお達しが出ている。お手水の桶の準備を済ませると、私は駐車場係の小鷹さんが見当たらないので会館の裏手にある喫煙所へ探しにいった。
「小鷹さーん、まもなくお客様のお戻りですよ」
お客様がいない時間帯、ふらっと煙草を吸いに行ってしまう小鷹さんは、東北訛りの穏やかなおじいさんだ。
「おう、連絡きたの。じゃあ仕事しないとね」
にこにこと悪びれもせず、道路の先が見える位置に移動した。
「お疲れ様です。遅くなってすみません」
伊織さんが事務所から降りてきて、私たちに声をかけた。私たちはお昼の休憩をいただいたけれど、伊織さんは今まで別の御葬家へお花を届けに出掛けていた。暑さのなか、分刻みの移動をこなしたはずなのに、いつもながらの凛とした佇まいだ。
みんなで外で待っていると全員が汗だくになってしまうので、お客様の車列が見えたら、小鷹さんが館内の私たちに知らせてくれる手筈になっている。
「お帰りでーす」
ほどなく小鷹さんが表から声を掛けてくれた。私たちはドアを開け放ち、玄関前でお客様をお迎えする。伊織さんの素早く流れるような動きに見とれながら、私もお客様がスムーズに移動できるよう気を配る。
「お水をお持ちしましょうか」
藤原さんが、顔色の悪い女性に駆け寄る。初七日法要の前は、お客様の疲れも出てくるので、体調の悪そうな方がいないか観察するのも大事な仕事だ。女性は控室で少し休むことになり、藤原さんがお部屋まで付き添う。昨夜から、くしゃみを繰り返す人もいたので、親族内で風邪をもらってしまったのかもしれない。
数分後、女性を除く全員が着席すると、初七日法要が始まった。
僧侶が木魚をリズミカルに叩く。御葬家の方は、移動の繰り返しで疲れたのか、うとうととする人もちらほら出てきた。
僧侶の合図で、藤原さんがお盆に載った焼香炉を取りに行き、回し焼香が始まる。
初七日法要は時間が短いので、左右両側から一基ずつ回す。私はタイミングを見て、残りの一基をお客様の手元に運ぼうとした。
その時だった。
祭壇の上に飾られたお花の陰から黒い靄のようなものが一瞬見え、六灯籠(ろくとうろう)の右片方がゆっくりと倒れてきた。
幸い祭壇の上から落ちることはなかったが、カターン、と音が鳴って、僧侶のお読経が一呼吸分だけ止まった。
伊織さんが音もなく僧侶の脇へ進み出て一礼し、長身を活かして素早く六灯籠を起こす。伊織さんが戻ってくると、式場内は何事もなかったかのように回し焼香が進んだ。気まずい空気は残ったものの、僧侶の法話も終わり、お清め室で精進落としのお席へと場は移った。
「先程は、大変失礼いたしました」
私と藤岡さんが配膳スタッフを手伝って、献杯のお飲み物をご用意する間に、伊織さんがお詫びをする。僧侶と喪主様は向かい合って祭壇の前に座っていたので、お二人に同時に謝る形となった。私は「伊織さんがんばれ」と心の中で祈りながら、横目で事の成り行きを見守る。
僧侶は苦笑いを浮かべつつも、品よく片手を顔の前で振った。
「いえいえ。驚きましたが……地震などでなくてよかったです」
一方、喪主様は渋面で伊織さんの顔を振り仰いだ。
「本当に、ご僧侶にお怪我がなくてよかったですが……安全確認はきちんとされているんですよね?」
喪主様は江東区内の病院で長く看護婦長を務めていた女性で、今は退職している。白髪をきりりとしたショートカットにまとめ、紫の色付きメガネをかけていた。
「勿論でございます。通常はあのようなことは無いのですが……誠に申し訳ございませんでした」
伊織さんが深々と礼をするのに対し、喪主様は口を引き結ぶ。
「済んだことなので、もう結構。それより食事を始めてください」
これってクレームになってしまった、ということだろうか。ハラハラしながら献杯のあと、式場の片付けに向かう。
椅子や焼香炉の片付けをしつつ、紺色のカーテンで仕切られた祭壇の裏手に回り、六灯籠が落ちた原因を藤原さんと調べてみる。
階段を裏側から見るような格好で、蛍光灯が取り付けられた祭壇の内側が見えて明るい。白木の祭壇は横板や屋根は重いけれど、他のパーツは女性でも軽々と持ち上げられる。六灯籠は、下から二段目に載っている。その名の通り、左右片方に三つずつ明かりが灯り、故人の輪廻転生の道筋を照らす役割をしているそうだ。三つ横並びのため、横揺れには強いけれど、前後に力がかかると倒れる可能性はある。
とはいえ、わざと後ろから押したりしない限り、式中に前へ倒れてきたりはしない。
「私は焼香炉をお客様から受け取る瞬間だったから、倒れたところは見てないのよね」
藤原さんが、腕組みをしたまま、上下左右から六灯籠を眺める。
「コードは結構長いんですね」
灯籠や透かし彫りの飾りに付いているライトは、裏側に電源コードが垂らされていて、祭壇の裏で電源タップにつながれている。祭壇と一番奥の壁の間には、使われていないパーツがパズルを組み合わせるように収納されている。
「そうね……うっく……ちゅん!」
藤原さんが両手で口元を多い、控えめで可憐なくしゃみをした。
「くしゃみ、可愛いですね」
私がつい言及すると、藤原さんは照れ隠しのようにハンカチでローズピンクの唇を押さえる。
「埃っぽいのよ、ここのカーテン。古すぎて……でも埃だけじゃなくて、何か匂いがしない?」
祭壇の真上には、換気口がある。顔を向けてみたが、そこから匂っているわけではないようだ。
「ちょっと私には分かりません」
私は首を捻るばかりだが、藤原さんは形のよい鼻をうごめかす。
「台風の日から時々、異臭の報告を受けているの。ほら、壁の隙間に雨水が漏ってカビが生えたりするでしょう。清澄会館も、建ててから結構経つから」
傷や汚れは目に見える箇所を修復すればよいけれど、匂いとなると対処が難しそうだ。
「お疲れ様です」
カーテン越しに、伊織さんの声が聞こえたかと思うと、伊織さんも祭壇の裏側にやってきた。
「伊織くん、遅かったわね。すぐ調べに来るかと思ったのに」
藤原さんの苦言に対し、伊織さんが苦笑した。
「お待たせしてすみません。実は、献杯のあと、陰膳のお寿司が一貫足りないことに末広さんが気付きまして」
『一貫足りない?』
私と藤原さんの声が重なった。陰膳とは、故人にお供えする分のお膳のことだ。
「足りないなんて、あり得ないわ。お料理が厨房から届き次第、確認しているもの」
藤原さんが断言する。私もうんうん、と横で頷く。お寿司は、大トロ・エンガワ・海老・サーモンの四貫一皿で、どれが欠けてもかなり目立つ。到着時のチェックで見落としたとしても、お供えする際に必ず気づくだろう。
「献杯のお供えで末広さんが気付いて、急ぎ厨房に連絡しました。お客様に気づかれないよう揃ったお皿と差し替え、足りない方を確認したのですが、確かにサーモンだけが無くなっていました」
伊織さんが、声を低くし淡々と状況を説明してくれる。藤原さんはしばらく腕を組み、考えていたけれど、すぐに唸りながら頭を抱えた。
「ううん、難しいわね。スタッフが意図的に一貫抜いたなら、説明がつくけど……私と西宮さん、末広さんはずっと一緒にいたからそれも無いわ。初七日法要の間に、誰かが食べてしまったのかしら」
私は記憶を辿り、あっと叫んだ。
「お部屋で一名様お休みでしたよね。ご気分が悪いって仰っていた女性の方……ってことはない、ですよね」
伊織さんも藤原さんも、首を振る。親族控室からお清め室に行くには、式場の前を横切らなければいけない。さらに、お清め室とパントリーを末広さんが行き来しているため、こっそり忍び込んでもすぐに見つかってしまうだろう。
「一貫無くなったとしたら、スタッフが駐車場へお迎えに降りたタイミングしかありませんね」
伊織さんが表情を曇らせる。
「実は、このところ続いていたポルター・ガイスト現象について、私なりに調べていたのですが、その結論がサーモンの件で覆されてしまいました」
「え、結論って、原因がわかったんですか」
私が期待を込めて、伊織さんの顔を見つめる。
「ひとまず、表に出ましょうか」
伊織さんはカーテンを開いて、どうぞ、と私たちを先に祭壇裏から出してくれる。
「式場の真後ろは、壁を隔てて倉庫になっています。最初のポルター・ガイスト現象はお読経の開始と共に倉庫の段ボールが崩れる、というものでした。中身はお茶で、大きさの割に軽い箱でした。天井ギリギリまで積み上がっていたものが、突然崩れたと聞いています。
同じ日のうちに、段ボールは積み直したのに、翌日また同じタイミングで崩れました。さらに次の日……昨日のことですが、式場の間接照明の板が外れて落下。入り口から祭壇へ向かって右側……カーテンレールのギリギリ手前辺りですね」
伊織さんが、私たちが立っているほぼ真上、壁に取り付けられた間接照明を指し示す。式場の天井より少し低い位置、壁沿いにぐるりと白色の磨りガラス風のアクリルパネルが渡されて、暖色の光が壁と天井に反射するように設置されている。式場内がふわっと優しい雰囲気になる演出だ。
ぱっと見ただけでは分からないのだけど、実は板の間に継ぎ目があり、中のLEDライトを交換するときに、簡単に作業できるようになっている。
「落下したのは一枚だけ。式場で作業していたのは生花部の紫藤さんひとりでした。大きな音に驚いて、慌てて式場から飛び出し、スタッフのいるパントリーに駆け込んだと聞いています」
昨日のポルター・ガイストに遭遇したのは、紫藤さんだったんだ。いつも手際よくお花を飾っているけれど、突然大きな物音がしたら、驚いてしまうのも無理はない。
「生花部の部長からは、お祓いをした方がいいんじゃないかと言われましたが、私は霊現象ではないと思っています」
伊織さんの言葉に、藤原さんも大きく頷いて、賛成する。
「当り前よ。どの故人様も丁重にお送りしているもの。未練があるとしたって、なごみ典礼の倉庫や式場を気に入るわけがないでしょう」
「ポルター・ガイスト現象は、国内外で有名な事例が実際にあるので、完全に否定できるものではありません。ですが、なごみ典礼で起こっていることには、法則というか……共通点があります」
伊織さんが祭壇を振り返り、次に間接照明に視線を移した。
「もしかして……音ですか」
私が、頭の中でうっすら考えていた仮説を口にした。
倉庫の段ボール箱は、お読経が始まった直後に二回とも倒れている。
生花部の準備作業は、お花専用の台を組み立てるので、金属質の音が響くこともある。
そして、今日もお読経の最中に六灯籠が倒れた。
伊織さんの瞳は、静かに私を見つめ返したあと、そっと伏せられた。
「仰る通りです。音と人の気配があるときに、反応があります。しかし、音が犯人ではありません。これを見てください」
伊織さんは、カーテンの裾を持ち上げ、私たちに見せた。紺色に紛れてわかりにくいけれど、細かな黒い毛がくっついている。
「……うっくちゅん!」
藤原さんがまたくしゃみをした。
「人の髪の毛ではないですね。猫か犬でしょうか」
私が黒い毛をそっとつまんで観察する。長さ五㎝くらいで、先端が細い。
「猫よ、絶対! 私、犬はアレルギーないもの」
藤原さんが鼻声で叫んだ。そういえば、お通夜のときにくしゃみをしていた人も、もしかすると猫アレルギーがあったのかもしれない。
「猫が住み付いているってことですね」
私が観た祭壇の上の黒い靄は、猫の体の一部だったのかもしれない。私の問いかけに、伊織さんは頷いて応える。
「はい。恐らくかなり臆病で、体格の小さな猫が、自動ドアが壊れた頃に、入り込んでしまったのだと思います。倉庫の段ボール落下は、棚の最上段で猫はくつろいでいたところへお読経が始まり、驚いて段ボール箱に飛び移ったものの、バランスを崩して落下した、と考えられます。間接照明の件は、隙間にもぐりこんでいたけれど、生花部の台車に驚いて、その拍子に板を壊してしまったのではないでしょうか。しかし、お寿司のサーモンの件はお手上げです。猫がお刺身と酢飯をキレイに一貫分だけ、食べられるわけがありません」
つまり、一連のポルター・ガイスト現象の犯人は猫であることは確実らしい。
「お寿司の件は、人間という説が有力なのね。スタッフではないと思うわ。お客様の注文されたものに手をつけるなんて。お寿司一貫のためにクビになりたくないもの。ところで式場の中にまだ猫はいるのかしら」
藤原さんが辺りを見回す。私も椅子の下や、司会台の陰など猫が隠れていそうな場所に目をこらすが、何もいない。伊織さんが整った眉を下げて、苦笑する。
「いるはずですが、猫は繊細な生き物です。我々を警戒しているうちは、出てこないでしょうね。今夜もお通夜でこの式場を使う予定ですから、出てきてくれればいいのですが……」
怯えている小さな黒猫を思うと、早く見つけ出してあげたくなる。家に連れ帰ることは無理でも、しばらく清澄会館で預かって、保護猫団体などに依頼することはできるのではないか。
「単純だけど、餌でも置いておくしかないわね。猫はあとで誘い出すとして、お寿司泥棒はどうしたものかしら」
部外者が入り込んでいるのだとしたら少し怖い。伊織さんが、頷きながら口元を押さえた。
「そうですね……一般会葬の行き交うお通夜の時間ならいざ知らず、今の時間帯、式場付近に無関係な人間がいればかなり目立ちます。しかし、一階部分なら、話は別です」
一階は、会館を訪れる様々なお客様が、待合わせ場所などに使う。お葬儀の相談、霊安室へのお参り、葬儀後のご精算など、日中も人の出入りは多い。中には近所の方が、お手洗いだけ借りることもあるけれど、大抵は駐車場係の小鷹さんがご来館目的を確認し、事務所に連絡する。
「伊織くんの言うとおりね。小鷹さんに、一階の出入りについて内線で聞いてみるわ」
藤原さんが、式場に備え付けられた内線電話に駆け寄る。そういえば私と藤原さんがお客様のお迎えで一階に降りたとき、お待ち合わせ風の男性がいたような気がする。
「小鷹さん、お疲れ様。さっき、お迎えの前に一階で待ち合わせをしている人って誰かいた?」
藤原さんは小鷹さんと短いやりとりを交わし、受話器を置いた。
「やっぱり平服の男性が、ソファに座っていたそうよ。霊安室に安置されている方のお身内、と仰ったみたいだけど」
「その方が、いまどこにいるかが問題ですよね」
館内に潜んでいるなら、お通夜のお客様の安全も脅かしかねない。探しに行かなきゃ、と私が意気込んだとき、藤原さんが言葉を継いだ。
「それで……実はまだいるみたいなの、同じ人が。一階のソファに」
「ええっ」
つい声が裏返り、体をのけぞらせた。
「そんなに堂々としてるなんて」
逃げも隠れもせず、一階にいるという。伊織さんは落ち着いた声音で言った。
「一階の男性がお寿司泥棒と決まったわけではありません。降りてお話を伺ってみましょう」
伊織さんが先に立ち、私たちは階段を降りる。エレベーターホールのソファに座っていたのは、小鷹さんと同じくらいの年齢の男性だった。
胸元にイラストの描かれた黒いTシャツに、薄汚れたベージュのチノパンを履き、腰にデニムジャケットを巻きつけていた。顔は日焼けして、オーブンで焼いた七面鳥の皮のようにツヤがあり、少し乾いたような質感だ。白髪交じりの髪も髭も、最後に手入れしたのは随分前のように見受けられた。
「失礼いたします、お客様」
伊織さんが、穏やかに声を掛けた。すると、男性はこちらを見向きもせずにのそりと立ち上がり、左右に揺れながら歩き出す。具合が悪いのか、少し苦しげな様子で故障した自動ドアをこじ開けようとした。
「お待ちください」
伊織さんはすぐに追いつき、男性の後ろから自動ドアに手を掛ける。逃げられないように閉じ込めるのかと思いきや、伊織さんは片手にぐっと力を込めてドアを開けた。男性は、ハッとした顔つきで伊織さんを見上げる。『話を伺う』と言っていたのに、何故帰してしまうのだろう。藤原さんも、真剣な眼差しで事の成り行きを見守っている。恐らく、本当に伊織さんが男性を帰してしまいそうになったら、自分が引き留めるつもりでいるのだろう。
「どうぞ。ご不便をおかけして申し訳ありません」
残暑の熱気と湿気が流れ込むなか、男性は、無言で会釈をし、駐車場へ出て行こうとする。
藤原さんのピンヒールが、カツっと音を立てて前へ出た。伊織さんが男性の背中に声を掛ける。
「よろしければ、ご連絡いたしましょうか」
えっ、とその場の誰もが動きを止めた。私も何のことだろうと、伊織さんと男性から目が離せなくなる。
「お探しの猫が、見つかりましたらご連絡差し上げます」
ふわーっと熱い風が吹き込む中、伊織さんの声は駐車場に反響するほど明瞭に響いた。猫、というと、式場に隠れているというポルター・ガイストの犯人だろうか。男性はぎくりと体を強張らせ、こわごわ伊織さんを振り返った。
「差支えなければ、お名前とご連絡方法を、お教え願えますか」
男性の瞳に、初めてきらりと意志の光が見えた。乾いた唇が震え、良く通る声で答えが返ってくる。
「自分は……大鷺(おおさぎ)と言います。住所と電話番号はありません」
私と藤原さんは顔を見合わせた。住所も無い、ということはホームレスなのだろうか。そう言われると、汚れの目立つ服装は外で生活しているからだと分かる。
「申し訳ありませんが……勝手に館内にお入りいただくのは困ります」
藤原さんが言いながら表へ出ていく。優しい声音だったけれど、きっぱりと言い切る言葉は少し強い。大鷺、と名乗った男性は、一度何か言いかけたけれど、膝に手をつき、ぺこりと頭を下げた。
「……ごめんなさい」
「ああもう、謝らないでください。そうじゃなくて、猫を探したいなら、そう仰ってほしかったんです。というか、伊織くん、この人は猫の飼い主で間違いないの?」
藤原さんが、弱った、というように頬に手を当てて尋ねた。伊織さんは頷き、大鷺さんに向かって語りかける。
「藪から棒に失礼いたしました。お洋服に……ズボンの裾に、猫の毛が付いていたので」
大鷺さんがパッと自分の足元に視線を移す。
「大鷺様がいつから、一階にいたのかは分かりませんが、私たちが、御葬家のお迎えで一階に集まったのを見計らって、式場へ上がられたのですね。二階にスタッフがゼロとは限りませんが、ほとんど人目に付かないだろうと思われたのでしょう。実際に、御葬家が戻られるまで、式場は無人でしたから、猫を探しに忍び込んだのですね。お供えのお寿司が無くなったせいで、我々は騒いでいたのですが、お心当たりはございますか」
伊織さんの、穏やかな調子の問いかけを、大鷺さんの声が遮った。
「ご、ごめんなさい。本当は、ゴミ箱から拝借した刺身で呼び出そうとしたんですけど、ダメで……焦ってお供え物に手をつけてしまいました。あいつ、多分、もう何日も餌を食べてないから、弱っていると思って、それで……」
大鷺さんの告白に、私たちは顔を見合わせる。
「それでも、出てこなかったんですね」
私が呟くと、大鷺さんは頷いた。
「そうなんです、クロ助のやつ、出てこなくて……結局、自分で食べました。自分も台風の日に、雨風で寝床を失って、貯めてた金も流されてしまって……」
「台風の日、ですか。それは大変でしたね」
伊織さんが労わりの言葉をかけると、大鷺さんの顔が悲しそうに歪んだ。
「あの夜、暴風雨の中、避難所に向かおうと思ったんですけど、きっと他のひとたちに嫌がられると思ってやめたんです。そしたら、ここの駐車場が道路の向こう側から見えて、ずっと電気が付いてて明るかったので……少しだけ雨宿りさせてもらおうと思って、そこの小部屋に入らせてもらったんです」
男性が示した先には、小鷹さんが詰めている警備室があった。夜間は鍵を閉めて帰る決まりだけれど、たまたま忘れたのかもしれない。
「明け方、手洗いを借りたらその拍子にクロ助が中に入り込んでしまったんです。ごめんなさい。本当に……許してください」
大鷺さんは頭を下げて、私たちを拝んだ。
「どうする? 伊織くん。お寿司一貫で警察を呼ぶのも可哀想だしねえ」
藤原さんが、唇を尖らせる。うんうん、と私も大きく頷く。事情も事情出し、猫を見つけ次第、無罪放免でもいいのではないだろうか。伊織さんは、大鷺さんをじっと見つめてしばらく考えていたけれど、やがて口を開いた。
「まずは、猫を探すのを手伝っていただきましょう。そのあと、少しお話があります」
「ああ、ありがとうございます! 何も飲み食いしてないんです、あいつ」
大鷺さんは猫に会えることが嬉しかったらしく、ぱっと顔を輝かせた。
「私も手伝ってもいいですか」
藤原さんにそっと尋ねると、くすっと藤原さんが笑った。
「いいわよ。どうせもう仕事は終わりだもの。生花部がお花を飾りに来る前に、見つけ出してあげて」
あまり時間が無いので、早速、私と伊織さん、大鷺さんは式場に戻る。扉を開けると、祭壇の向こうでかさり、と何かが動く気配がした。
「クロ」
ちっちっち、と大鷺さんが舌を鳴らしながら猫を呼ぶ。ふと私は思いつき、パントリーからお椀にお吸い物の残りを入れて戻ってきた。ふわっと鰹出汁のよい香りが漂う。同時に、ひょこひょこと祭壇の後ろから壁沿いを小さな黒猫が歩いてきた。
「クロ助!」
子猫は飼い主に一瞥をくれると、お椀に駆け寄ってくんくんと匂いを嗅いだ。おつゆの温度はもう下がっているから、猫舌でも飲めるらしく、すぐに口をつけ、ぺろぺろと飲み始めた。満足げにゴロゴロと喉を鳴らし、美味しそうに目を細める。
「「かわいいですね」」
私と伊織さんの声が被り、二人で笑みを交わす。騒がしい幽霊ならぬ、お騒がせの黒猫は、しばらくすると舌なめずりをしながら飼い主に抱きかかえられた。
「では、私と大鷺さんは、館長を交えて話をしてきます。西宮さん、お疲れ様でした。また付き合わせてしまってすみませんでした」
伊織さんが、けほんと咳払いをする。館長を交えて、ということは、大鷺さんは警察に突き出すことはされないまでも、何らかの形で責任を負わされるんだろうか。
少し心配だったけれど、私が口を挟めることではない。
「ありがとうございました」
大鷺さんにもお礼を言われて、会釈で返す。お通夜の仕事もあるので、仕方なく式場を後にした。
それから、二週間が過ぎ、残暑も落ち着いてきた頃。なごみ典礼清澄会館は、新しい噂で持ちきりになっていた。末広さんが、緑茶に氷を放り込みながら、嬉しそうに語る。
「なんでも、前の仕事はデパートの駐車場係やったらしいで」
小鷹さんとともに働く駐車場係が一名増えたのだ。日焼けした精悍な顔が、往年の映画スターを思わせる、ということで、年配の女性スタッフの注目を集めている。
「まさに、権藤館長の大岡裁きっちゅうわけやな」
そう、新しいスタッフは、黒猫の飼い主だった大鷺さんだ。大鷺さんは権藤館長の采配で、正直に事情を話した人柄と経歴を認められ、晴れて駐車場係として採用された。家は社宅の一部屋をあてがわれたという。ペットは禁止なので便宜上、クロ助は保護猫団体に引き取られたが、社内で飼いたいという人がすでに現れたらしい。
「西宮さん、わかる? 大岡裁きって」
藤原さんに言われて、緑茶をいただきながら頷く。
「ええ、祖母が好きだったので」
エンディングテーマを口ずさむと、「それは遠山の金さん」と突っ込まれた。お奉行間違いだったらしい。火葬場からお客様が出発した、と連絡が入り、私たちは立ち上がって椅子を片づける。
表に出ると、外は雨が降り出しそうな曇り空だった。涼しい風が吹いて、もう秋だな、と分かる。新しい駐車場係は張り切って誘導灯を片手に、先輩について駐車場を行き来している。
「小鷹さん、大鷺さん、もうすぐお帰りです」
私たちが声を掛けると、二人は嬉しそうに振り返り、こちらへ走ってきた。先日は具合の悪そうだった大鷺さんは、よく食べて眠れているのか、軽快な動きに変わっている。
「一件落着ね」
「はい」
秋風に目を細めて、微笑む藤原さんの隣で、私は大きく頷いた。
(了)