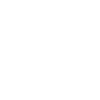ポスターでビールのアピール ~瀬戸内杏介の謎解き~
「次は、飯田橋です。乗り換えのご案内です。東西線、有楽町線……」東京メトロ南北線を降り、階段を急ぎ足で登る。自動改札の先に理香さんが立っていて、手を振って出迎えてくれた。
「リーちゃん、遅くなってごめんね」
息を切らしながら挨拶する俺に、理香さんはニッと笑って、地上を示す斜め上を指差す。
「ううん、大丈夫よ。JRの駅前の立ち飲み屋さん行ってたから」
「やっぱり飲んでたんだ」
どうりで、頬も少し赤くなってるわけだ。
「キュー君、見てよこの写真」
彼女は、スマホに映った赤い飲み物のジョッキの写真を見せてくれた。
「さっき飲んでた季節限定のアセロラサワーなんだけど、度数が十%もあるの。ちょっと気にならない?」
「十%! サワーで珍しいね。飲んでみたいかも」
前のキウイサワーも酸味がしっかりあって美味しかったのよね、という感想を聞きながら、二人並んで地下鉄飯田橋駅のB3出口に向かった。
五月も後半となると、暑い日は二五度以上の夏日となり、GWまでのうららかな気候からの急激な変化に体も随分疲れやすくなっている。「こんな日は飲んで英気を養うに限る!」という理香さんの提案に乗り、まだ火曜日だけどIn the Torchを訪れることになった。
「いらっしゃいませ、ワイン飲み放題やってます!」
一杯やり始める人も多い一九半過ぎ、威勢のいい呼び込みをしている店員の前を通り過ぎ、裏路地を歩いていく。やがて、すっかり見慣れたやや小さめの三階建ての建物が見えた。
「混んでるかな? 満席だったりして」
「In the Torchが火曜の二十時前に満席だったら、すぐに二号店が出せるね」
ジョークを飛ばしながらスチールの階段をカンカンと勢いよく登っていく。
分厚いドアをゆっくりと開けると、店内は外よりも大分涼しかった。ピアノのジャズのBGMが静かに流れている。
「いらっしゃいませ。おっ、天沢さんこんばんは! 久登、連絡ありがとな」
「行くなら杏介に先に知らせておいた方がいいかと思ってさ」
「こんばんは、瀬戸内君」
マスターである杏介が出迎えてくれる。先客は奥のカウンターの二人だけで、いつも通りの穏やかな空間だった。
「オレはこのくらいの人数が、お客さん一人一人と話せて好きなんだよな」
「杏介はよく言ってるよな」
雑談をしながら、誰も座っていない店の入り口に近い方のカウンターに通される。エンジ色の本革製のメニューを受け取った。
「瀬戸内君、今日のオススメのお酒は?」
「天沢さん、よくぞ聞いてくれました! こんな暑い日に恋しくなるだろうと思って、ドルトムンダーを入れてます!」
「わっ、ホントに? じゃあ二つ頼んじゃおうかな。あと、合いそうな肉料理もお願い」
「了解でっす!」
謎のお酒を注文し、彼女は楽しそうにダークブラウンの髪を揺らした。何のお酒かも想像がつかないので、気になるのを通し越して少し不安だ。
「ねえねえ、理香さん。ドルトムンダーって何?」
「あら、キュー君は単語聞いて何が思い浮かぶ?」
「え……サッカーのドルトムントかな」
ブンデスリーガというドイツのサッカーリーグに所属する名門クラブだ。
「そう、名前の通り、ドルトムントって都市で造られてるお酒よ。ドイツと言えば……?」
「あ、ビールか!」
「正解!」
理香さんに代わって杏介が小さく叫びながら、栓を開けたややでっぷりしたビール瓶二本と背の高いビアグラスを置いてくれる。
「ドルトムンダーっていうビールの種類だな。ドルトムントは確かにサッカーも有名なんだけど、ビール大国のドイツの中でもかなりのビール生産都市なんだぜ」
「へえ、知らなかった」
「よし、キュー君、飲もう飲もう!」
理香さんに急かされ、慌てて彼女のグラスにビールを注ぐ。淡い金色は、いつも飲んでいる生ビールよりも透き通って見える。綺麗な宝石のようだ。
「すごく素敵な色でしょ。見た目が美しいから『ブロンド・ビール』とも呼ばれてるの。それじゃキュー君、今日もお疲れ様。乾杯!」
「乾杯!」
カチンッとグラスをぶつけて、一日の疲れと暑さを流すようにグッとビールを飲んでいく。苦みが少めで口当たりが良いのでどんどん喉に入っていき、グラスを口から離すと「ぷはっ」と爽快な息が漏れた。
「さっぱりしてて飲みやすいなあ」
「でしょ? ドルトムンダーの特徴なの」
グラスを照明に透かしながら眉をクッと上げて嬉しそうに語る理香さんは、乾杯の一口で既にグラスの半分まで減らしていた。
「製造のときに、ホップの効果を控えめにしてるの。だから苦みが薄くなってる。でも麦芽の甘みもそこまで目立たないから、バランスが良くてするするっと飲めるのよね」
「確かに。海外ビールだけどクセが少ないもんな」
これはビールのホップ独特の苦みが苦手な人でも飲みやすいだろう。
「飲みやすいからどんどん飲めちゃう。あとは、このビールに合う肉料理が欲しいところだけど……」
「はい、天沢さん、お待たせしました」
タイミングを見計らったかのように、杏介が白い丸皿をコトリとカウンターに置く。そこには、太めのソーセージが二本と、フライドポテトが乗っていた。
「ドイツ料理、カリーヴルストです」
「カリーヴルストって……杏介、これただのソーセージだろ?」
「いいや、久登、これはれっきとしたドイツ料理なんだぜ。ほら、よーく見てみろよ」
得意げに説明を始める彼に促され、赤と濃い黄色で彩られているソーセージに顔を近づける。すぐに、食欲をそそる香辛料の香りが鼻をくすぐった。
「カリーはカレー、ヴルストはドイツ語でソーセージって意味だ。焼いたソーセージにケチャップとカレー粉をまぶしただけなんだけど、シンプルなこれが美味いんだよ」
「どれどれ、いただきます」
「ワタシも!」
理香さんと一本ずつ分け合い、フォークで刺してそのままがぶりと齧ってみる。
しっかり焼いているので外はカリッとしているけど、中はふわりと柔らかい。その食感のコントラストが面白くてやみつきになりそうだ。ケチャップにはソースを混ぜているのか、バーベキューソースのような味付けになっていて、酸味控えめで肉料理にマッチする。そして、たっぷりかかったカレー粉は、スパイシーなだけではなく、時折ピリリとした辛みも残す。カレー粉がたくさんついている部分とそうでない部分で味が全く違うので、食べるごとに味が変わって、ボリュームたっぷりのソーセージでも飽きることなく食べられてしまう。
もちろんビールとの相性は言わずもがな。肉の塊を頬張って熱々、そして脂っこくなった口に一気に押し寄せる冷気と清涼感。喉を通って体中に爽やかさが駆け巡り、暑くなり始めたことで少しずつ蓄積していたであろう疲労を吹き飛ばしてくれる。まさにこの時期にピッタリのお酒と料理だった。
「さすがドイツ、ビールの本場は伊達じゃないわね!」
満足そうな理香さんの唸りを聞きながら、ふと店の奥のカウンターに目を遣る。
この店で初めて見る男女が二人、A4くらいのカラー紙を見ながら首を傾げていた。
「ううん……やっぱりこれ確認した方がいいですか」
「そう、ね……問合せしてみようか」
何かに悩んでいるらしい。気になっていると、杏介も同じだったようで、スッと奥のカウンターに移動していく。空いたグラスにカラフェから水を注ぎながら、さりげなく話しかけた。
「良い色彩ですね。何かの宣伝のビラですか?」
二人は一瞬顔を見合わせたものの、三十代くらいの女性が「マスターになら話してもいいかな」と許容するように小さく頷く。俺より少し年上と思しき、シルバーのハーフリムのメガネをかけた男性が口を開いた。
「僕達はビールメーカーに勤めていて、海外ビールの輸入・販売を担当してます。
先週からかな、今年の夏に向けて、新しいドイツビールのポスター案を広告業者に依頼してました。今日、一つ目のデザインラフ案が出てきたんですけど、ちょっと引っかかるところがあって……」
そう言って彼がポスターの案を開いて掲げた。「彼らは僕の友人なんで、一緒に見させてもらってもいいですか」と断りを入れてくれた杏介に軽く手招きされ、俺と理香さんも足早にカウンターを移動した。
カラーのA4用紙の中央には、海外メーカーらしい背が低めの瓶ビールの写真が載っていた。そのビールの注ぎ口から色とりどりの花が顔を覗かせている。紙の下の方に、『お洒落に乾杯』というキャッチコピーが入っていた。
「ふむ……オレには違和感ないように見えますけど、引っかかるところというのは……」
「このキャッチコピーなんです」
今度は女性がハキハキと話し始める。薄手のジャケットにラメ系のアイシャドウで、パリッとした印象から、彼女は男性の上司なのだろう。
「ポスターを依頼するときは、あまりこちらのイメージとズレないよう、事前にデザインのイメージを作って出します。私達の作ったものでは『オシャレに乾杯』とカタカナのキャッチコピーを出していたのに、デザイン案では『お洒落』の部分が漢字になってたんですよね。
別に漢字がダメというわけではなくて、ただ、やっぱりカタカナと比べて堅くなってしまう気がして……。直接メールで受け取った上司も、先方から特に補足はなかったと言っていました。明後日その会社からプレゼンを受けるんですけど、できたらそれまでに社内の意見をまとめたいので、わざわざ漢字に変えた意図を知りたいよねって彼と話していました」
なるほど、言われてみれば「お洒落」より「オシャレ」の方が軽いテイストのように思える。大勢の人の目に留まるポスターだからこそ、変更が特に引っかかったのだろう。
さて、これも「お酒に纏わる謎」と言える。しかも謎のテーマはビールで、今俺達が飲んでいるのもちょうどビールだ。であれば当然、酩探偵である理香さんの出番——
「その謎、オレに任せてください」
俺の思考を遮る、目の前の黒シャツのマスター。顎ひげを親指で優しく撫でながら、杏介が自信満々に言い切った。
「久登、お前の考えていることはよく分かる。理香さんに謎解きをお願いしようとしてたんだろ。しかし! このIn the Torchはオレの城だ。だから今回はオレが解いてみせるぞ」
「本当、ですか?」
上司の女性は、不安げに杏介を見上げている。いきなり謎を解き明かしますとバーの店主に宣言されたら、俺が彼女でも戸惑ってしまうだろう。
しかし、本来こういう場で探偵役を務めるはずの理香さんは、元の席から持ってきたビールをグッと飲んだ後、顔の前で拍手をした。
「いいね、瀬戸内君! 名推理期待してるわ」
「天沢さん、ありがとうございます。頑張りますね」
こうして俺は、新規の来客もなく暇になった杏介の謎解きを見守ることになった。
「ううむ……」
五分後。サックスも加わったやや古めかしいジャズサウンドが流れるIn the Torchには、カウンターに両手を付き、重苦しい表情で思考に耽っているマスターの姿があった。よく磨かれたカウンターの上には「ただいまオーダーストップです」という貼り紙をテープで留めたカラフェが載っている。注文より推理を優先するバーがあるだろうか。
体を揺らしながら、時折「オシャレ……オシャレ……」と呟く杏介と、そわそわと彼を見守る隣のビールメーカー社員二人。推理に没頭する様子は理香さんに似てなくもないけど、彼のように熟考中は何も口にしないか少し水を飲むくらいが普通だろう。お酒をかぱかぱと飲みながら謎解きをする理香さんはやっぱり特殊なんだと思い知らされた。
「リーちゃん、助け舟出さなくていいの?」
行き詰っている杏介を見つつ理香さんに訊くと、上機嫌に首を横に振る。
「大丈夫よ。閃けば案外簡単なはずだから」
「簡単って……あれ? その言い方、リーちゃんひょっとしてもう分かってる?」
髪は解いてないものの、立ち飲みで既に結構飲んでいたようなので、彼女の頭は冴え渡っているのだろう。
「さあ、どうかしらね」
右手をひらひらさせながらおどけたように微笑んで答えをはぐらかし、彼女は杏介の方に向き直った。
「瀬戸内君、小休止のときで大丈夫だからビールのお替りくれる?」
「あ、はい、分かりました。ううん、難しい……久登、何か浮かぶか?」
「え、俺? いきなりだな」
理香さんもよくやることだが、唐突に意見を求められる。どうして探偵というのは急に話を振ってくるのか。
「どうだろう……そうだ、このビールの味が、日本のビールに近かったんじゃないかな。だから、それが伝わるように、あえて漢字にした」
「まあたしかにジャーマンピルスナーとか日本のビールに近い種類もあるけど……」
「いや、それはないと思います」
会社員の男性が、俺と杏介の会話に割って入った。身を乗り出したタイミングで少しズリ落ちたメガネのフレームを、右手でスッと直す。
「僕達も飲んでみたし、この案を作ってくれた広告会社の担当者の方にも試飲してもらいましたけど、結構華やかな味わいでした。花のブーケを思わせるフレーバーで、だからこそカタカナで『オシャレ』ってキーワードを入れました」
「でも漢字になっていたと。やっぱり何か理由があるなあ……」
杏介はまたり唸った後、これまでの推理を振り払うように「ああっ、もう!」と首をブンブンと動かす。
「よし、気分転換! 天沢さん、ドルトムンダーお替りですね? 久登は?」
「ああ、じゃあ俺も貰おうかな」
「オッケー」
ウィスキーやリキュールが並ぶの横、日本酒や割るためのジュースを冷やす業務用冷蔵庫からビールを取り出し、俺達の前でシュポンッと開栓したときだった。
「あれ……?」
一瞬フリーズした杏介は「ちょっといいですか」と上司の女性から瓶ビールのポスターを受け取り、ジッと眺める。
そして、得心したようにニンマリと微笑んだ。
「ありがとうございます。なるほど、そういうことだったのか」
「え、じゃあ……」
ばっちりメイクの目を見開く彼女に、杏介は頷きながらカラフェの「ただいまオーダーストップです」という貼り紙を外す。
「謎は解けました」
「えー、今回の事件のポイントは、漢字ならではのトリックです」
カウンターの内側で、杏介はポスター案の紙を片手にうろうろと歩きながら話し始めた。どこか往年の探偵を彷彿とさせる。
「キャッチコピーに書かれている『お洒落』の『洒』という字、『酒』という字にすごく似てますよね」
「確かに……僕も学生の頃は一緒の字だと勘違いしてました」
男性が答える。間違って「お酒落」と書いてあっても、なかなか気付かないだろう。
「二つの字の違いは、線があるかないかです。つまり、『酒』の≪酉≫から一本線を取ったら『洒』になる」
ニッと笑った杏介は、手元に新しいビールを用意し、栓抜きで勢いよく開栓した。
「飲むために栓を抜いた、ってことです」
「あっ!」
「そういうことね!」
隣の会社員二人が、同時に声をあげた。
「まさに『洒落』みたいな答えですけど、漢字の説明もつきます!」
「ちゃんと考えたうえでの遊び心ってわけね」
部下の男性に続いて、上司もしてやられたとばかりにニヤリと笑う。
「広告会社の担当の方が、なぜこんな手の込んだことを考えたのかは分かりません。一つ考えられるとすれば、SNSでの宣伝ですね。例えば今オレが解いたように『なぜ漢字にしたのか』なんて謎解き形式で投稿すれば、バズる可能性も高いと思います」
おそらく、杏介の推理の通りだ。なぜクライアントが提案したカタカナではなく、あえて堅い印象になりかねない漢字にしたのか。PRの過程でそのカラクリを明かした方が、世間で注目されやすいだろう。
「天沢さん、いかがですかね?」
「お見事ね、瀬戸内君。ワタシの見立ても同じよ」
「やったぜ!」
理香さんは、杏介が謎を解くと宣言したときと同じように、もう一度顔の前で小さく拍手してみせる。やはり、彼女も解けていたのだ。ひょっとしたら杏介にビールのお替りを頼んだのも、栓のヒントを与えるためかもしれない。
「先方が考えてくれた小ネタのおかげで、PR戦略を色々膨らませそうね」
「はい、良いポスターが完成しそうです。マスター、ありがとうございました。この店に来てみて良かったです」
「いえいえ、オレの推理がお役に立ったなら何よりです」
三人の会話の様子を、理香さんは柔らかい表情で見つめていた。
それにしても、お酒に関する謎解きが大好物のはずなのに、理香さんはなんで今回は杏介に譲ったのだろう。
俺の中に残った小さな謎を解くために、理香さんに話を振ってみる。
「ねえ、謎解き披露しなくて良かったの?」
すると彼女は、「うん」と頷いて、耳打ちするように顔を寄せた。グッと近づいた彼女のぱっちりした目を見て、ドキリと心臓が跳ねる。
「あの二人、初めてお店来たんだと思うし、ビールメーカーの人ならお酒好きの知り合いたくさんここに連れてきてくれるかもしれないからさ」
「ああ、そういうことか」
In the Torchもまだ開店二年目、店としては固定客を増やして売上を安定させる時期だ。
今日は、杏介とバー自体の評判を上げて、ファンを増やすのに一役買ったのではないだろうか。もちろん、自分がいつでも気軽に飲める場所を確保したいという下心もあると思うけど、この店のために杏介に花を持たせたのだろう。
人を幸せにするお酒を目指す理香さんらしい心配りで、そういう優しいところも好きだな、と思えた。
「よし、じゃあ事件も無事に解決したってことで、ドイツビールで乾杯しませんか? さっき皆さんに飲んで頂いたものとは別の、なかなか手に入らないドルトムンダーが入ったんです!」
「瀬戸内君、それ良いわね。二本ちょうだい!」
指をパチンと鳴らした理香さんが、謎が解けてホッとした表情を見せている二人に声をかける。
「あの、良かったらご一緒してもいいですか? お酒大好きなんで、メーカーの方のお話、聞いてみたいです」
お誘いを受けた上司の女性は、嬉しそうに顔を綻ばせた。
「はい、ぜひ。マスター、私達にもそのビール二本ください!」
「合計四本ですね、少々お待ちを!」
やがてカウンターには杏介が飲む用を含んだ五本のビールが並べられ、俺達は全員で乾杯しながらビール談義に花を咲かせたのだった。
〈了〉

酔いが回ったら推理どき
酩探偵天沢理香のリカー・ミステリー
- 著:六畳のえる
- イラスト:倉秦
- 発売日:2022年6月20日
- 価格:770円(本体700円+税10%)