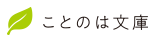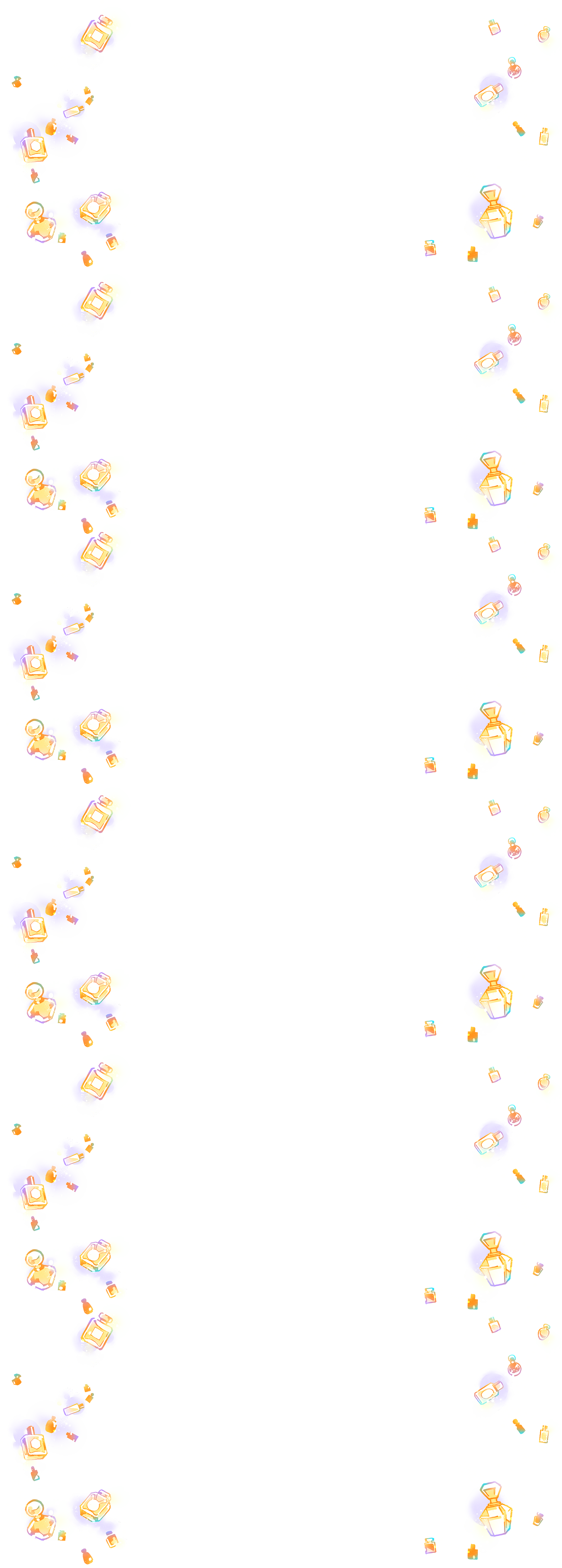
再会までのマセラシオン
私の毎日は、香りに彩られている。朝起きて飲む、ハーブティーの香り。焼けたパンと、溶けるバターの香り。それから、家を出る前にひと吹きする、香水の香り。私、の大切な人がくれた、名前と同じの香りだ。白い花を集めてブーケにしたような「勇気の出る香り」が、一歩足を踏み出した瞬間に匂い立つ。優しい香りに背中を押されて、今日も私の一日は始まる。
理系の大学院に通う私は、目下論文の執筆中だ。スラスラ英語を書けるわけもなく、夜までパソコンの前で唸る日々が続いている。
「はあ、疲れた……」
体を引きずるようにしてアパートに帰りつき、郵便受けのダイヤル錠を回す。何気なく開けた瞬間、ふわりと香りが漂い出た。はっとして覗き込むと、一通のエアメールが入っていた。
「さん……?」
遠くパリにいる恋人の名を呟く。鼻を掠めたのは、別れの時彼に贈った、ほんのりスパイシーな香水の香りだった。
葵さんことさんは、私に「勇気の出る香り」をくれた調香師である。名前の由来であるタチアオイのようにまっすぐ高みを目指す彼を、私は「葵さん」と呼んでいた。
彼の香りから、思い出が昨日のことのように次々と蘇る。
葵さんと出会ったのは、一年と少し前のこと。彼は香水店の店主兼調香師、私はその店のアルバイトとして、数か月を共に過ごした。その期間は色々と大変なこともあったのだけれど、いつしか私たちは惹かれ合い、めでたく付き合うことになったのだった。
しかし、思いが通じた喜びもつかの間、遠距離恋愛がスタートした。電話やメールはするけれど、もう一年近く会っていない。素直に言えば、寂しかった。葵さんは調香師として、私は学生として、頑張らなければいけない時期だとはわかっているけれど。
靴を脱ぐのももどかしく、荷物をソファに放る。封を開けると、香水の香りが強くなった。中身は便箋が一枚と、名刺サイズの小さな封筒。畳まれた便箋を開くと、美しい文字が並んでいた。
茉莉さんへ
お元気ですか。忙しくされていると思いますが、無理はせず、自分のペースで頑張ってくださいね。
さて、今回はちょっとした息抜きのお誘いです。いつでも良いので、午後から半日分の時間を、僕にいただけないでしょうか。
日本に戻ることはできませんが、あなたにお見せしたいものがあります。この手紙が届いたら、連絡をください。
志野立葵
p.s. 小さな封筒は、まだ開けないでくださいね。
なんだかよくわからない。手紙が届いたのに、連絡しろだなんて。とはいえしっかり浮かれていた私は、早速空いている日をメールで伝えた。五月の今はサマータイム期間なので、パリと東京の時差は七時間。あちらは午後の仕事が始まった頃だろう。返事は気長に待つ気でいたのだが、数分後には返信があった。まじめに働いているのか、ちょっと心配になる。
「土曜日の午後一時、小さな封筒を持って新宿御苑の大木戸門に……?」
いったい彼は、何をしようとしているのだろう。謎は深まるばかりだった。
約束の土曜日、私は新宿御苑の入り口近くに立っていた。街の喧騒は遠く、爽やかな緑の匂いに包まれている。
時間ぴったりに、手の中のスマホが振動した。ディスプレイに表示された葵さんの名前を見ただけで、一気に胸が高鳴る。震える指を慎重にスライドさせ、スマホを耳に当てた。
「はい、茉莉です……」
「こんにちは。こうして話すのは、ずいぶん久しぶりな気がしますね」
ざわめきの中に、葵さんの声が聞こえた。私の好きな、柔らかくて温かい声。たった一言で、胸がぎゅっと絞めつけられる。
「今、どちらにいらっしゃいます?」
「言いつけ通り、大木戸門の前にいますよ」
説明不足にむくれているのがわかったのか、電話の向こうで葵さんが小さく笑った。
「では、そのまま中へ。プラタナス並木のある方は、わかりますか」
新宿御苑は何度か来たことがあるので、大体の方向は覚えている。歩きながら、葵さんがぽつりぽつりと喋る声を聞いた。
「色々と、考えました。離れていても、茉莉さんに伝えられるものはないか」
砂利を踏み締める音に混じる声を聞いていると、まるで隣を彼が歩いているようだった。
「それで、やっぱり僕らを繋ぐものは『香り』だと思ったんです」
前方に、濃緑のプラタナスが見えてきた。向かい合って並ぶ木々に守られるようにして、開けた庭園が広がっている。青々とした芝生。そして――。
「どうです? 綺麗でしょう」
花壇から零れ落ちそうなほどに、咲き誇るバラたち。近づくにつれ、甘く華やかな香りが濃さを増していく。
「その中に、花弁の外側が濃いピンクで、内側がクリーム色の花はありますか」
「えっと……あっ、ありました!」
特徴的な見た目はひときわにぎやかで、すぐに見つかった。
「『ダブルデライト』という品種です。美しさと芳香、“”を兼ね備えた花、と言われています」
顔を寄せ、匂いを嗅いでみる。柑橘系のような爽やかな香りだ。
「では、背丈が低めで、薄いピンク色の花は?」
「それなら、さっき見かけたような」
幾重にも重なる花びらが可憐で、目を引いていた。
「アンブリッジ・ローズです。これも香りの強い種ですが、先ほどとは違って甘い香りがするはずです」
確かに、爽やかさもありながら甘い。葵さんのヒントを聞いて花を探すのは、宝探しのようで楽しかった。
「葵さんも、ここに来たことがあるんですか?」
「ええ、まだ学生の頃ですけれど」
「じゃあ私たち、時を越えて同じ香りを共有したってことですね」
葵さんの返事がなかった。あれ、電波が悪いのかな。
「……ええ、そうですね」
声色から、今の沈黙は照れていたからだとわかった。私まで恥ずかしくなってきて、慌てて口を開く。
「えっと、葵さんは今どこにいるんですか」
「自宅のベランダですよ。すぐ横に、先ほど言ったバラの鉢植えがあります。茉莉さん風に言えば、場所を越えて香りを共有したというところでしょうか」
「もう、からかわないでください!」
私の言葉には照れるくせに、自分から言うのは平気なのだ。きっと電話の向こうでは、ちょっと意地悪な顔をしているのだろう。懐かしくて、少し寂しくなった。
新宿御苑を出た後は、フランスから上陸したカフェでお茶をした。同じ店がパリにもあり、私たちは同じメニューを注文した。見ている風景は違うけれど、花の香りもコーヒーの香りも、きっとパリと東京で変わらない。私たちはこの瞬間、確かに香りで繋がっていた。
「離れていても、こんな風に繋がることができるんですね」
「そう感じてもらえれば、僕としては成功です」
満足げに微笑む葵さんの顔が浮かぶ。
私は論文を書くのに四苦八苦していると愚痴を話し、葵さんは今構想を練っている新作の香水の話をした。気づけばあっという間に、二時間が過ぎていた。
「そろそろ、最後の行き先に向かいましょう。封筒を開けてみてください」
バッグの中から小さな封筒を出し、封を開ける。中には二枚のカードが入っていた。一枚はレジ横によく置いてある、店名や地図が入ったショップカードだ。
「『ワインショップ』?」
「そこに行って、店員さんにカードを渡してください。僕のサインが入った白いカードです」
もう一枚のカードは、白地に金の縁取りがされていた。筆記体で、T.Shinoと書かれている。
プレゼントに、ワインを用意してくれたということだろうか。店の最寄り駅は神楽坂で、電車に乗って移動した。
「神楽坂の街は、パリの風景に似ていると言う人もいます。昔からフランスと交流があって、フレンチレストランなども多いんですよ」
夕暮れの中、入り組んだ裏路地や階段を上ると、やがてレトロなランプの下がった小さな建物が見えてきた。
ドアを押して、店に足を踏み入れる。板張りの床が小さく軋んだ。カウンターも壁も温かな色の木材で、ほっとする空気が流れていた。
「いらっしゃいませ」
カウンターの向こうに佇むのは、品の良い初老の男性だった。私はカードを取り出し、恐る恐る見せる。彼はにっこりと頷くと、うやうやしく一礼した。
「ご用意いたします。どうぞ、こちらへ」
店の奥にある一室に通され、テーブルにつく。一度姿を消した店員さんはすぐに戻ってきて、テーブルに小瓶を載せた。スタイリッシュな、四角い縦長のフォルム。側面に彫り込まれた「perfume」の筆記体が、明かりを受けてきらりと光った。葵さんの店で使われていた香水瓶と、同じものだ。
「これは……?」
店員さんは微笑みを湛えたまま、私が握りしめたままのスマホを手で示した。
「こちらではお預かりしていただけですので、志野様にお尋ねください」
店員さんの背中を見届けて、スマホを耳に当てる。頬が熱を持っているのがわかった。
「受け取っていただけましたか?」
「はい。これは、葵さんが調香した香水ですよね。どうしてあのお店に?」
「ワインの保管条件がピッタリだったからです。香水の、『マセラシオン』に」
アルバイトをしていた頃の記憶を辿って、口を開く。
「香料を混ぜ合わせた後に熟成させること、ですよね」
ただ香料を混合しただけでは、香水は完成しない。時間を置くことで、アルコールと香料が化学反応を起こし、馴染んでより調和のとれた香りに変化するのだ。その過程を、フランス語で『マセラシオン』という。
「その通り。長いものでは、半年をかけることもある過程です。僕が思いついたのは、それこそワインのように、何年もかけて熟成させる香水でした」
「何年も……」
「長い時間をかけて、変化していく香りを楽しむものです。来年はまた、違う香りになっているでしょうね」
一旦言葉を切ると、葵さんは微かに緊張を滲ませて言った。
「来年も、その先も、変わっていく香りを茉莉さんに知ってほしいと、僕は思っています」
まるでプロポーズのような言葉に、目の前が滲む。それが葵さんの願いなら、私はわがままを一つ。
「次は、一緒に香水を開けましょう。さもないと、パリまで押しかけますから」
「それはそれで、楽しそうですね」
二人で笑い合うと、胸のつかえが消えていくような気がした。
会わない間に気持ちが離れてしまうかもしれないと、ずっと不安だった。変わることに、怯えていた。でも、大丈夫だ。不安を塗り替えるほどの希望を、葵さんがくれたから。彼はいつだって、香りを通して私に新しい世界の見方を教えてくれる。
これは未来を約束する始まりの香水。どんな香りがするのだろう。期待を膨らませ、私は香水瓶の蓋に手をかけた。

嘘つきジャスミンと
秘密の多い香水店
- 著:miyabi
- イラスト:細居美恵子
- 発売日:2021年3月19日
- 価格:759円(本体690円+税10%)
書店でのご予約はこちらの予約票をご利用ください