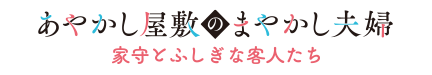「私の『推し』?」
――今日は特別、頑張ろうって決めていた。
思い立ったら吉日、という言葉を胸に秘め、私は朝の身支度をした。ベージュのスプリングニットに、軽いキルティングのスカートは動きやすい膝上の丈だ。とはいえ、春先はまだまだ冷えるから、タイツとレッグウォーマーを忘れずに。最後に髪をシュシュで結べば、完成だ。
「……うん、よしっ」
私は自室を出て、一階へ向かった。早朝のひんやりとした空気がお屋敷に満ちている。古い板張りの廊下は長く奥まで伸びている。途中、ふすまや扉がいくつかあって、居間や台所、洋風の応接室などに繋がっている。私はすっかり馴染んだ古民家の風景に、目を細めた。
ここに住み始めてから、一ヶ月半になる。
私が七瀬真琴から、英真琴になったのも同時期だ。
――ことのきっかけは、お見合いだった。
私は十二歳の頃に両親を事故で亡くし、叔父さんに引き取られた。とてもお世話になったけれど、あの家には……正直、あまり良い思い出はない。
私が十八になり、叔父さんは家を出るように告げた。とはいえ、叔父さんの会社の手伝いや家事で毎日が精一杯だった私には、収入を得るための仕事もない。何もないまま放り出されようとしていた私に降ってわいたのが、お見合い話だった。
そこで出会ったのが――
「――おはようございます、真琴さん」
低く聞き心地のいい声がした。階段の上を仰ぎ見ると、背の高い男の人がいた。
「おはようございます、千尋さん」
私はにっこりと微笑んだ。
英千尋さん、この人がお見合いの相手で――一応、私の旦那様だ。
一応、というのには訳がある。
私が千尋さんにお見合いの席で持ちかけられたのは、いわゆる『契約結婚』だからだ。
このお見合いが破談になったら、もう行く場所がない――と、泣いてしまった私に千尋さんは契約の『条件』を持ちかけた。
その条件とは、この家を一緒に守ることだった。
ここは千尋さんの大学時代の親友である、遠原さんという方が住んでいたお屋敷だ。遠原さんは今、留守にしていて、その間、このお家を千尋さんに託したのだという。
階段を下りてきた千尋さんは私を見て、わずかに首を傾げた。
「今日は……その、随分軽装なんですね?」
「あっ、これですか?」
私は自分の格好を改めて眺めた。
「実は……今日、お屋敷とお庭の大掃除をしようと思っていて」
「大掃除、ですか」
「はい。普段のお掃除ではなかなか行き届かないところを重点的にしようかなって。あっ、もちろん千尋さんの仕事の邪魔にならないようにしますね」
千尋さんは小説家だ。それも売れっ子なのでとてもお忙しい。
「それは……気にしなくても大丈夫ですが。あまり無理はしないでください」
「はい、このお家は広いですから。ちょっとずつしますね。まずはいつも通りお庭から行ってきます」
「なら、俺も朝の散歩に行きます」
私と千尋さんは連れ立って玄関から庭へ出た。
遠原邸の庭はとても広い。元気な子供がめいっぱい走り回っても、まだ余るぐらいだ。敷地に沿って生け垣があり、こんもりと丸く刈られた植え込みがあって、立派な松の木や桜の木が植わっている。そんな庭の光景が、朝日を浴びて光り輝いている。
私は裏庭の納屋から箒を持ってきて、大きな桜の木の周囲を掃き始めた。
すると、どこからともなく、ちりん、と鈴の音がした。とことことこちらに向かってくるのは三毛猫だ。ただしその尻尾は二つに分かれている。
「たまちゃん、おはよう」
猫又というあやかしであるたまちゃんは、私の足元にすり寄ってきて、ごろごろと喉を鳴らした。
散歩に出ると言っていた千尋さんがふと立ち止まった。
「もうこの家には慣れましたか」
「はい、それはもう。どこになにがあるかもばっちりです」
「ああ、というより……この家のあやかしに、です」
――あやかし。
それは尋常では視えざるものの、総称。
そして私が千尋さんの『契約結婚』の相手に選ばれた理由でもある。
私は昔から、普通の人には視えないものが視えていた。お見合いの時、たまたまそれを知った千尋さんは遠原邸の――あやかしが集い、憩うというこの家を一緒に守って欲しいと、私に提案したのだ。
そう、たまちゃんだけではない。あやかしはこの家のそこかしこにいて――
「真琴どの、真琴どの、おはようございます」
老獪な口調と共に、桜の木の根元から出てきたのは――白い犬だった。歩くたびに、ふわふわの毛並みを揺らし、わふわふと息をしている。
「木霊さん、おはようございます」
木霊とは木に宿る精霊で、あやかしの一種だ。この家の木霊さんは桜の木に宿っている。
「今から木のお掃除をしますね」
「頼みましたぞ。あ、そうだ特に根元の近くを念入りに……って……」
木霊さんはゆっくりと私の後ろを仰ぎ見た。そこには事態を静観していた千尋さんの姿があって――
「――きゃあああっ!」
木霊さんは絹を裂くような乙女っぽい悲鳴を上げて、姿を消してしまう。脱兎の如く逃げ出してしまった木霊さんに、私は思わず千尋さんを振り返った。
千尋さんは軽く溜息をついた。
「まぁ、怖がられるのはいつものことです」
「千尋さん……」
なんと声をかけていいか分からず、私はそっと目を伏せた。
木霊さんが逃げてしまったのは、別に千尋さんが悪いわけではない。
千尋さんは悪いあやかしを退治する――退魔士でもある。
といっても、その力を千尋さんは無闇に使ったりはしない。私が見たことがあるのは一回だけ。あやかしが人に害をなすかもしれない、という時だけだ。それも結局は未遂に終わったので、私は千尋さんがあやかしを祓うところは見たことがない。
けど、そういう力自体を木霊さんや他のあやかしは恐れているようだった。もちろん気にしないあやかしもいるのだけど……。
千尋さんも自分のことを『あやかしに好かれる性質ではない』と話している。
その緩衝役として、私が『家守』のパートナーに抜擢されたわけだ。
「木霊さん、おくびょ……ええと、怖がりさんですからね」
来た頃には桜の花が咲いていた木を仰ぐ。今では瑞々しい葉が生い茂る木は、さわさわと風に揺れていた。
千尋さんと朝ご飯を食べ終えてから、私が台所で一人、片付けをしていると──窓も開けていないのにふわりと風が吹いた。肩越しに後ろを振り返れば、スーツ姿の若い女性がビジネスバッグと脱いだパンプスを片手に立っていた。
「やあやあ、おはよう、真琴くん!」
「あっ、狭霧さん。おはようございます」
この人は狭霧天音さん。千尋さんが本を出している出版社の方で、千尋さんを担当している編集者さんだ。家がご近所なので、出社の前にこうしてしばしばうちを訪ねてくる。ご飯を共にすることも珍しくはない。
「今日はもう食べ終わっちゃったんです。残り物でもよければお出しできるんですけど」
「うん、頼むよ。白飯と真琴くんのぬか漬けがあれば十分さ。あとできれば味噌汁と小鉢なんかがあると嬉しいな。あっ、千尋に見つかるとまたうるさいから、ここで食べてしまうよ」
「ふふ。はい、ただいま」
狭霧さんのリクエスト通り、メニューはご飯とお漬け物、新たまねぎと油揚げのお味噌汁、小鉢はたけのこと菜の花のおひたしだ。いそいそと椅子を持ってきた狭霧さんは、台所の調理台で朝食を食べ始めた。私はその横で再び食器を洗い始める。
「いつもは朝食の時間に来られるのに、今日は遅かったんですね」
「うん、いわゆるフレックスというやつだな」
「ふれっくす……」
「社員の裁量でいつ出社してもいいという制度さ。ただしその分、退社時間は遅くなるが……」
肩を落としていた狭霧さんだったが、ご飯とにんじんのぬか漬けを頬張ると、ぱあっと笑顔を浮かべた。相変わらず見ていて気持ちのいい食べっぷりで、料理を作った側からするととても嬉しい。
「真琴くん、もう結婚生活には慣れたかい? 何か困ったことがあったら、すぐ私に相談したまえよ」
「ありがとうございます。あ、そういえば……」
私は今朝の出来事を思い出した。千尋さんを見るなり木霊さんが逃げてしまった話だ。訳あって狭霧さんはあやかしの存在を知っているので、思い切って相談してみた。
狭霧さんはお味噌汁を一口飲んで、うーんと唸った。
「まあ、君の言うとおり、千尋は退魔士だから仕方ない部分はあるな」
「そう、ですよね……」
「千尋も別に気に病んではいないだろう。今は君という頼れるパートナーもいることだし」
狭霧さんが綺麗に片目を瞑る。
私は曖昧な笑みを浮かべて頷きながらも、内心では、千尋さんのことを慕ってくれるあやかしが少しでも増えないものかと、密かに願っていた。
小鉢のたけのこを食べていた狭霧さんが、ふと尋ねてきた。
「ところで今日は、随分とラフな格好をしているんだね?」
「千尋さんにも言われました。あんまり似合わないでしょうか……?」
私はあまり服を持っていない。これの他にせいぜい二、三着程度だ。それもブラウスやセーターにスカート、といった格好が多い。
「そんなことないさ。むしろいつもと雰囲気が違ってとてもいいね。狭霧さんは君のすらりと伸びた足や、纏めた髪の奥から覗く白いうなじに夢中さっ」
「え、ええと……」
私が返答に困っていると、唐突に台所の扉が開いた。
「――狭霧さん、セクハラまがいの発言はやめてください」
そこには仏頂面の千尋さんが立っていた。
「やあ、千尋。おはよう」
「おはよう、じゃありません。またそうやってタダ飯喰らって……」
「何を言う、私は君たち夫婦の後見人だぞ」
「頼んだ覚えはありません」
にべもなく言い放つと、千尋さんは溜息を吐きながら冷蔵庫を開けた。そうしてコップに麦茶を注ぐと、一気に飲み干す。千尋さんと狭霧さんのいつものやりとりに、私はそっと心の中で苦笑した。
「とにかく早く出社してください。原稿はメールで送っておきましたから」
「まぁまぁ、そう急ぐもんでもなし」
「いいから仕事しろっ」
のんびりとお茶を啜っていた狭霧さんに、千尋さんから喝が入る。
肩を怒らせている千尋さんの手から、私はそっと空になったコップを受け取る。千尋さんは軽く頭を下げつつ、踵を返した。
「真琴さん、その人をあんまり甘やかさないでください。空の果てまでつけあがりますから」
「あ、あはは……」
千尋さんが台所から出て行く。まったく意に介した様子のない狭霧さんが、肩を竦めてみせる。
「あんな堅物を好くあやかしなんているのかねえ?」
私は同じように、乾いた笑いを返すしかなかった。
朝食の片付けを終え、渋々ながら出社していく狭霧さんを見送った。
「ようしっ」
右手にはハタキ、左手には濡れ雑巾。口元はマスクで覆った。
大掃除の準備は万端だ。
私は手始めに二階の一番奥の部屋へ赴いた。十畳ほどの薄暗い部屋に、障子窓の明かりが差していて、宙に舞う埃をきらきらと浮かび上がらせている。ここは物置になっていた。古い本や玩具、庭仕事の道具などが置きっぱなしになっている。窓を開けて換気をしながら、置いてある物のなかから踏み台を取り出して、その上に乗った。これで天井にも手が届く。掃除の基本は上から下へ、だ。
「結構、埃が溜まってそう……」
とりあえずぱたぱたとハタキで天井の埃を下へ落としていく。くすんだ木目を見つめていると、急に天井がたわんだ。
「え?」
もしかして古くなっているのかな? 思わず手を止めると、突然──
「──あのう」
と、聞き慣れない声と共に、逆さまの子供の顔が天井から出てきた。
「っ、ひゃああああ!」
私は驚いて、踏み台から転げ落ちそうになった。なんとかバランスを保ってこらえる。
「あっ、あわわわ、ごめんなさい。脅かすつもりはなかったんですう」
逆さまの幼い表情が慌てる。ぱちぱちと目を瞬かせて、私はその顔を見た。
おかっぱの小さな女の子だった。肩から上が天井からにゅっと生えている。赤い着物を着ていて、まるで生きている時代が違うようだった。
「もしかして……あやかし、ですか?」
「え? あ、ああ……『妖』という意味ですね? そうです、そうです。っていうか、人間の方が嫌じゃありません? 天井裏に人間いたらそっちの方が怖くありません?」
「は、はぁ、まぁ、確かに……」
若干、早口で聞き取りづらいところがあるけれど、言葉が通じるようで良かった。あやかしの中にはたまちゃんのように喋ることができない子もいる。
「あたし、天っていいます。気軽にお天ちゃんとでも呼んでください。……お姉さんは最近、ここのお家に来た人ですよね?」
「あ、はい。英真琴です」
「英……ってことは、お嫁さんかぁ。なるほど、感慨深いです。あ、気にしないでください。あたし、結婚とか平気な方なんで。まぁ、いや、さすがに突然ギャルとか連れてこられたらびっくりするっていうか解釈違いなんですけど。でも真琴さんなら大丈夫です」
何が大丈夫だろう? 私の疑問を置き去りに、お天ちゃんは続けた。
「あー、そのう、実はあたし、密かに推してるんですよね……ちひろっち」
「ちひろっち?」
それってもしかしなくても、千尋さんのこと?
首を傾げる私に、お天ちゃんはもじもじしながら答えた。
「うへへ……そうなんです。元々メガネ属性はあったんですけど、あの寡黙で、でも冷たすぎない感じ、ほんともう性癖をセンターに入れてスイッチっていうか」
「あ、あの……ええと、つまりどういう……?」
「しまった、パンピーの前で興奮しすぎた。要するに、あたし、オタクなんです。しがない千尋推しの……うーんと、ファンってことです」
ファンと聞いて、私ははっとした。
「それはつまり……千尋さんが好きっていうことですよね?」
「はい、そうなんです!」
大きく頷くお天ちゃんを見て、私は思わず目を輝かせた。
狭霧さんは『あんな堅物を好くあやかしなんているのかねえ?』なんて言っていたけれど……いた。ここにいたんだ!
「千尋さんはお天ちゃんのことをご存知なんですか?」
「いえ。そのう……あたし、見守る期間が長すぎて、ちょっとこじらせちゃってるっていうか。今更、声かけづらいなぁって思ってて。あ、そう! それで!」
お天ちゃんがずいっと顔を寄せてくる。
「できたら一度、話してみたいんですよね。でも素直におしゃべりできないっていうか……。そこで、良かったら、真琴さんに取り持って欲しいというか。あたしを紹介してくれたらなぁって」
「……っ! はい、それはもう喜んで。任せてください!」
願ってもないことだった。私が二つ返事で了承すると、お天ちゃんの顔がぱあっと華やいだ。
「わぁ、本当ですか? やったあ! 真琴さん、イケメン! そこに痺れる憧れるぅ!」
「そ、そんなに褒めないでください……えへへ」
喜ぶお天ちゃんを見て、ついつい本音が零れる。
「私、とっても嬉しいんです。千尋さん、あやかしたちに怖がられることもあるから……」
「そうなんですか?」
「はい。でも本当は心優しい方なんです。だからお天ちゃんが千尋さんを好きって言ってくれて、私、自分のことのように喜んじゃいました」
お天ちゃんは私を見つめて、大きな瞳をぱちぱちと瞬かせている。
饒舌だったお天ちゃんが何も言わなくなってしまったので、私は首を傾げた。
「お天ちゃん?」
「……ハッ。す、すみません。ええと、はい。そういうわけで、よろしくお願いします」
「はい、もちろんですっ」
大きく頷くと、お天ちゃんはきょろきょろと視線を左右に彷徨わせる。が、気を取り直したように言った。
「あたし、天井伝いに移動しますので。居間で落ち合うというのはどうですか?」
「わかりました。またお昼時になったら千尋さんも下りてこられると思うので、いいタイミングで出てきてくださいね」
ふと、そこで私は気になったことを尋ねた。
「ところでお天ちゃんはどういったあやかしで……」
そこまで言いかけて気づく。
おかっぱ頭に着物姿の女の子、お屋敷に隠れて潜んでいるということは……。
もしや、あの……幸運をもたらすという、座敷童?
うん、そうだ。だってついさっき私を幸せな気分にしてくれた。間違いない。
「ああ、申し遅れました。あたしは──」
「あっ、大丈夫。分かりました!」
「え、ほんとですか? あたしって自分で言うのもなんだけど結構マイナージャンル──いや、まあ、いいか」
「お天ちゃん……?」
「なんでもありません、どうぞよろしくお願いします」
「はい。では、また居間でお会いしましょうね!」
お天ちゃんは控えめに手を振りながら、天井裏へと戻っていく。掃除の途中だったことを思い出し、私は再びはたきを振りだした。今度は鼻歌交じりに。
そして待ちに待ったお昼時がやってきた。
今日のお昼ご飯のメインは初がつおのお刺身だ。刻んだしょうがとみょうが、ねぎ、それに初穂紫蘇といった薬味をたっぷり添えている。スナップエンドウと春キャベツの焼き浸しには、ふんわりとしたかつお節を乗せて。小鉢はくずし豆腐の冷や奴。ご飯は青豆を混ぜて塩味をつけた。
居間の食卓に意気揚々とおかずを並べる私に、千尋さんは座布団の上に座りながら、小首を傾げた。
「何か……楽しそうですね」
「ふふ、そうですか?」
弾むような声で答えた私の視界に、すすすっと黒くて丸い頭が見えた。はっとして顔を上げると、そこには天井からぶらさがっているお天ちゃんがいた。
「お、お、お邪魔しま〜……す」
「ひゃっ、あ、お天ちゃん!」
突然、現れたお天ちゃんにびっくりしてお茶碗を取り落としそうになる。一方の千尋さんはというと、眼鏡の奥でぱちりと一つまばたきするだけだった。
「真琴さん、このあやかしと知り合いですか?」
「えっ、ああ……その、さっき偶然出会って……」
千尋さんはじーっとお天ちゃんを見上げている。お天ちゃんはもじもじと天井に顔を埋めたり戻したりしていた。そうだった、お天ちゃんはこう見えて千尋さんに今まで声をかけられなかった恥ずかしがり屋さんだ。私がちゃんと仲をとりもってあげなくちゃ。
「ご紹介しますね、千尋さん。この子はお天ちゃんです」
「はぁ、そういう名前だったのですか」
「……もしかしてお天ちゃんのことご存知なんですか?」
「まぁ、見かけたことぐらいは。いつもすぐに逃げられますが」
困ったように言う千尋さんに、私はある可能性に気づいた。千尋さんにとってはお天ちゃんもまた木霊さん同様、自分を恐れているあやかしの一人に分類されているんじゃないか。
私はすぐに伝えたい気持ちにかられた。そんなことはないんです、むしろお天ちゃんは千尋さんが大好きなんですよ、と。
けど、それを私が言ってしまうのは野暮だ。私は視線が合いそうで合わない二人に、再度話しかけた。
「今日、物置のお掃除をしていたらお天ちゃんに会ったんです。はじめましての私にも明るく話してくれて……」
「さすが真琴さんですね」
感心したように千尋さんが言う。その口調はいつも通り平坦だけど、私にはどこか寂しげに聞こえた。た、確かに私は千尋さんの代わりに『この家に集うあやかしの面倒を見る』という役目でいるけれど……!
私は話の矛先をお天ちゃんに変えた。
「お天ちゃんは千尋さんに言いたいことがあって来たんですよね?」
「え……あ、その……う」
物置での饒舌ぶりはどこへやら、お天ちゃんは口元を天井に埋めて、もごもごとしている。私は弾まない両者の会話に段々と焦ってきた。
「千尋さんはお天ちゃんのことどう思います?」
「どう、とは」
「だってほら、幸せを運ぶ座敷童ですよ? そんな子が会いに来てくれたんですから──」
「えっ?」
声を上げたのはお天ちゃんだった。私も思わず「えっ」と返す。千尋さんは私とお天ちゃんを見比べた。
「ああ……。このあやかしは座敷童ではないですよ」
「え? そ、そうなんですか?」
「はい、天吊るしというあやかしです。天井からぶらさがって人を見るだけで、特になにもしません」
「とくになにもしない……」
「ええ」
勘違いが恥ずかしいやら情けないやらで、私は呆然とする。するとお天ちゃんが控えめに声を漏らし、肩を震わせた。どうやら笑っているようだった。
「ふふ……。あ、すみません、真琴さん。あたし、ちゃんと自己紹介してなくて」
「ご、ごめんなさい、私こそ早とちりしちゃって」
「いえ。でもおかげでちょっと緊張がほぐれました」
お天ちゃんは天井からにゅっと顔を出した。大きく息を吸い、大きく吐いた。そして千尋さんを真正面から見つめる。……逆さまだけど。
「突然ですけど──あなたのこと、ずっと推してました!」
「……おして?」
「ああ、えっと大好きって意味です! ファンサして!」
「……ふぁんさ?」
「あたし、ちひろっちの好きな仕草があるんです。眼鏡くいってして!」
態度が豹変したお天ちゃんに戸惑いを隠せないのか、千尋さんは視線を彷徨わせた挙げ句、助けを求めるように私を見た。私はうんうん、と頷く。千尋さんはどこか釈然としない面持ちで眼鏡のブリッジを押し上げた。
「キャーッ、いただきました、星三つ! あとチェキのポーズはハグでいいすか? って、ダメだ、あたし写真に写らないんだった。てへ」
「……ええと」
「とにかくいつも応援してます、今日はお疲れ様でしたぁ!」
言うだけ言って、お天ちゃんは天井裏へと姿を消した。
お天ちゃんの迫力に気圧されたのか、千尋さんは唖然として天井を見上げている。
「お天ちゃん……」
私はというとなんだか感極まってしまった。
自分の気持ちを素直に伝えるというのは、簡単そうでとても難しいと思う。けど、お天ちゃんはそれを成し遂げたんだ……と思うと。
「千尋さんも、お天ちゃんも……本当に良かったですね……!」
「もしや、ついていけてないのは俺だけですか?」
目尻の涙を拭う私を見て、千尋さんはしきりに首を捻っていた。
昼食を終えて物置の掃除を再開すると、天井からお天ちゃんが顔を出した。
「真琴さん、さっきはありがとうございました。おかげで大満足です!」
「お天ちゃん」
私は掃除の手を休め、天井を見上げる。
「ううん、私、あまりお役に立てなかったですけど……。千尋さん、あんまりその……ピンときてない感じでしたし」
「あ、いいんです。塩対応はむしろ解釈一致なので」
「しお……かいしゃく……?」
「気にしてないってことです。むしろちひろっちらしくていいなぁって」
「確かにそうかも。……ふふ、お天ちゃんって千尋さんのこと本当に好きなんですね」
「真琴さん……。あの──」
お天ちゃんはやや目元を赤らめながら、続けた。
「あたし、真琴さんも推してもいいですか……?」
「へ? お、おして?」
「はい。さっきは、こんなあたしのために一生懸命になってくれて……。すごく嬉しかったんです。だからあたし、真琴さんのことも大好きになっちゃったんですよね」
「お、お天ちゃん……!」
「あのちょっとしてほしいポーズあるんですけど……。にゃん、ってしてもらっていいですか?」
「え? あ、あの、ええと……にゃん?」
言われるがまま頭に両手をもってきて、猫の耳を作ると、お天ちゃんの目が輝いた。
「くううう、可愛い! 猫! 萌えずにはいられないッ! ごちそうさまでした、お疲れ様でしたぁ!」
お天ちゃんは先ほど同様、嵐のように去って行った。
……ちょっとよく分からない部分はあったけれど、ともかく喜んでもらえたようだ。
私ははたきをぽんぽんとリズムよく動かし始めた。鼻歌はますます高くなるばかりだった。
物置の掃除を終えると午後三時近くになっていた。そろそろおやつでも準備しようかと一階の台所に赴くと、千尋さんが急須からお茶を注いでいるところだった。
「あっ、すみません、千尋さん。お茶なら私が……」
「あぁ、いえ。ちょうど仕事に一区切りついたところでしたから。真琴さんもそろそろ休まれては?」
「……はい、ではお言葉に甘えて」
天気もいいので、私たちは居間の縁側でお茶をすることにした。お茶請けは柏餅だ。千尋さんが淹れてくれた濃いめの緑茶に、柏の葉でくるまれた甘いお餅がよく合った。
そこへ、りんと鈴の音が鳴った。庭の方からたまちゃんがやってきて、ひょいと千尋さんの膝に乗る。千尋さんは手でたまちゃんを撫でてあげながら、湯呑みに口をつけた。
そよそよと緑風を受ける千尋さんの横顔は穏やかだ。たまちゃんを見つめる伏し目がちの瞼の縁に、長い睫が生えそろっている様を見ていると、なんとなく目が離せない。
「お天ちゃんが言うことも分かるなぁ……」
「なにがですか?」
「えっ、あ」
心の声が漏れてしまっていたらしい。私は慌てて言いつくろった。
「ええと、その、わ、私も──千尋さんを推し? ちゃおうかなぁって」
「おし……」
千尋さんはしきりに眼鏡の弦を弄りはじめた。
「推し、というのは……その、大好きだと──いう意味らしいですが……」
珍しく歯切れの悪い千尋さんの言葉は、頭の中で噛み砕くのに時間がかかった。
そして理解した瞬間、かあっと頬が火照るのを自覚する。
「い、いえ、あの、はい……その」
「……おそらく、誤用かと思われます」
「そ、そうで、しょうか……。ま、また今度、ちゃんとお天ちゃんに聞いておきますね。あ、あはは」
なんとも言えない沈黙が流れる。私は必死にお茶を飲んでいるふりをした。
りりん、と再び鈴の音が鳴る。私たちを見て、たまちゃんだけがのんびりと不思議そうに小首を傾げていた。

あやかし屋敷のまやかし夫婦
家守とふしぎな客人たち
- 著:住本優
- イラスト:ajimita
- 発売日:2022年3月19日
- 価格:770円(本体700円+税10%)