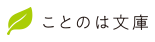佐々倉大貴は崩れない
同じクラスの佐々倉大貴は、生真面目で融通の効かない面倒な男だ。表情もあまり豊かな方ではない。
「沖島さん、これの正確な数値を測って記入し直してほしい」
佐々倉に見せられた紙には、文化祭で使用する物の情報が記載されている。その中のひとつ、『イートインスペース案内用のスタンド看板』のサイズに丸がついていた。
「あー……準備室に仕舞っちゃったから、あとで測る」
「今すぐに」
そんなに急ぐようなことでもないはずだと眉を潜める。夏休みにクラス全員でこうして学校で集まるのは貴重なことで、今はもっと時間をかけなければいけないことがたくさんあるのだ。
「でも先に他のことを進行したいし。てか、サイズざっくり書いたじゃん」
「僕は正確な数値を測った上で進めたい。でないと、本番直前になにかあったら困る」
少しも曲げる気がないらしく、淡々とした口調で話しながら佐々倉が私の机にメジャーを置いてくる。今すぐ測りに行くのは彼の中で決定事項らしい。
「はいはい。測ってくればいいんでしょ」
準備室はいろんなクラスの荷物が次々に積まれたり押しこまれていくため、その中から見つけて測る作業は少々面倒なのだ。だけど佐々倉を納得させないとしつこそうなので仕方がない。
「僕も行くから、ちょっと待ってて」
「え、佐々倉も行くの?」
「沖島さんひとりだとまた適当に測りそうだから」
じゃあ、最初から佐々倉が測りに行けばいいじゃんという言葉をぐっと飲み込んでため息を漏らす。まあ、私もざっくりと書いたのが悪い。
佐々倉は自分の席に戻り、ペンケースを開ける。おそらく数値を記入するためのペンを取りに行ったのだろう。すると、近くを通りかかった市瀬さんたちが佐々倉に声をかけた。
「佐々倉くん、うさちゃんシュークリームが好きなの?」
机の上に置いてある佐々倉の大好物のうさちゃんシュークリーム見て、市瀬さんを含めたクラスの女子たちが驚いている。あの堅物そうな佐々倉が、ファンシーなおやつを好んでいるのは意外だと感じるのは頷けた。あまりにもミスマッチすぎる。
「シールも全種類コンプリートしている」
何故か得意げに佐々倉が言った。そこで女子たちの笑いが起こる。
うさちゃんシュークリームにはシールがついていて、全八種類。それをたくさん持っている佐々倉はことあるごとに私たちリーダーへ配る資料に貼り付けてくるのだ。間抜けな顔をしたうさぎが『がんばっ!』などと言ってくるのがちょっとイラッとくる。
「佐々倉くんって可愛いね〜」
あの佐々倉が可愛い?と首を捻る。一緒にいることは多いけれど、一ミリも思ったことがなかった。
男子は可愛いと言われるのは複雑なのかと思いきや、本人は表情を崩すことなく真面目な顔で「ありがとう」と返している。その反応はどうなのかと呆れてしまう。けれど、そういうところが佐々倉らしいのかもしれない。
「ねえ、佐々倉って可愛いの?」
近くで今後の制作スケジュールを立てている古松さんに聞いてみると、固まってしまった。たぶんこれは真剣に考えている。人と話すことが得意ではない彼女なりに、必死に言葉を探しているのだろう。
少し間を置いてから、古松さんが口を開いた。
「……ギャップが可愛いってことじゃないかな?」
「ギャップねぇ」
男子がああいったファンシーなものが好きだったら意外だとは思う。でも例えば、爽やか系男子の石垣が持っていたら彼女の趣味かと疑われそうだ。佐々倉はそういったことに無縁そうだからこそ、一番ギャップがあるかもしれない。
「佐々倉くんはなんていうか……とっつきにくそうだから、可愛いものが好きだったり、シールを集めているのを知ると親しみが湧くのかも」
「なるほど」
少し前までは佐々倉と話すことすらなさそうだった市瀬さんたちが和やかな雰囲気で笑っているのを見て、確かにそういう効果はありそうだと納得した。
うさちゃんシュークリームに関する話が終わったらしく、佐々倉がこちらへ歩み寄ってくる。
「沖島さん、準備室に行こう」
私はメジャーを握り、じっと佐々倉を見上げた。愛想なんて欠片もなく、どちらかといえば冷たそうな印象を覚える。やっぱり可愛いとは思えない。
ふたりで廊下を歩いていると、急に佐々倉が「あ!」と声を上げて立ち止まった。
「なに? どうしたの」
何事かと身構えてしまう。しゃがみ込んで床に手を伸ばした佐々倉は、指先になにかをのせて私に見せてくる。そこには赤と黒の小さな物体がいた。
「てんとう虫だ」
「あ、うん……だね」
よく気づいたなと思いつつ、ちゃんと空いている窓から逃してあげている佐々倉の姿をぼんやりと眺める。
「佐々倉ってギャップがあるらしいよ」
「それは初めて言われたな。中学の頃は、真面目でメガネ以外特徴がないって言われてた」
佐々倉の言う通り、真面目そうなメガネ男子という印象が最初はあった。だけど足元の虫を大事そうに指にのせて逃してあげたり、ファンシーなものが好きだったり、第一印象とは結構違っている。
「それでもいいって思っていたけど、最近は沖島さんとか石垣たちが羨ましいと思うようになったな」
「なんで? 石垣は……まぁ男女に人気あるし、羨ましがられるのはわかるとして。私のどこが羨ましいの」
むしろ私はああはなりたくないと思われる側な気がする。言葉はキツいし、人とのコミュニケーションはいまだに得意ではない。友達だって少ない方だ。
「自分を持っていて、かっこいいところ」
「そんなの佐々倉だって持ってるじゃん」
文化祭の準備で誰かと衝突したり問題に打ち当たっても、誰よりもブレないのは佐々倉だと思う。
「僕はルールに囚われているだけで、沖島さんたちみたく意志の強さはあまりない」
再び歩き出しながら、私は佐々倉の言葉に耳を傾ける。誰かの話に対して自分の考えを言うことはあっても、佐々倉自身の話をしてくれることは今までなかった。なので、これが初めて聞く彼の本音のように感じる。
「佐々倉は自由が羨ましいんじゃない」
「自由?」
「ルールを常に守ろうとしてる佐々倉は、心のどこかで自分が不自由だと思ってんじゃないの」
「……そうかもな」
私には強い意志を持っているように見える佐々倉も、なにかしら抱えているものがあるようだった。ただ相談事には不向きな性格な私は、佐々倉の言葉に隠された感情を掬い上げて、心を軽くするようなうまい言葉は浮かんでこない。
「うちらのクラスがまとまってるのは、遠藤さんや石垣たちの声がきっかけだったけど、佐々倉が細かいところまでちゃんと見てくれているおかげで順調に進んでるじゃん」
私にでもわかるのは、この人がいなければ文化祭準備は今ほど順調には進んでいないということだ。だから誰かを羨ましく思うことがあっても、佐々倉は佐々倉のままでいい。私はそうであってほしい。
「てかさ、佐々倉って個性強くない? 小姑みたいにうるさいのに真顔でボケるし、ファンシーなおやつ好きだし」
「真顔でボケたつもりがない……」
「とにかくさ、佐々倉はおもしろいよ。まあ、面倒なときもあるけど」
「沖島さんは僕を上げて落として楽しんでるよな」
上げて落としている気はない。そういう佐々倉だから、私は一緒にいて楽しいのだ。それにこうして誰かと気楽に話せるようになったのは、佐々倉たちのおかげ。入学当初は私の言葉で誰かを傷つけたり、嫌われることを恐れて、ヘッドフォンで周囲の声を遮断していた。だからあの頃の私に教えてあげたい。もう少ししたら、私の言葉を必要としてくれる人たちができるよって。
準備室に着いて、積み上げられている物の隙間を通っていくと、私たちのクラスのスタンド看板を発見した。測れるように周りの荷物を少し動かしてから、メジャーの先を佐々倉が持って、本体を私が持つ。
「そうそう、あとさ」
先ほどの会話に追加して、私の思っていることを口にする。
「手を抜かずに頑張ってる佐々倉はかっこいいと思う」
静まり返ってしまい、妙な気まずさに包まれる。普段は会話のキャッチボールが速い佐々倉の反応が鈍いことが原因だ。
「……どうも」
「なにその素っ気ない返答。さっき可愛いって言われてありがとうって即答してたくせに」
不満だったのかと佐々倉を見やると、驚きの光景にあやうくメジャーを落としそうになってしまった。
「あ、いや……言われ慣れてないからびっくりした」
そう言って視線を逸らした佐々倉の耳は、ほんのりと赤くなっている。
なにその反応。そんな佐々倉知らないんだけど? と心の中で文句のような言葉が溢れ出てくるものの喉の奥で詰まって出てこない。
表情は相変わらず崩さないくせに、隠しきれていない佐々倉の感情を見つけてしまって、私にもその感情が伝染していく。心臓が大きく弾むように鼓動を繰り返し、頬が熱い。
「冗談だけど」
苦し紛れの一言を足すと、佐々倉が顔を上げた。そして何故か不服そうにわずかに眉を寄せる。
「……沖島さん、上げて落とさないでほしい」
私の発言で一喜一憂する佐々倉は珍しくて、目に焼き付けるようにまじまじと観察してしまう。表情をあまり崩さないので、感情の振れ幅が小さいように思っていたけれど、わかりづらいだけだったのかもしれない。
「あとメジャーもっとピンと張って。正確な数値じゃなくなる」
「はいはい。えーっと65センチかな」
「いや、64.8センチだ」
「細か!」
またいつか機会があれば、もう一度くらい言ってみようかと思う。
〝佐々倉は面倒だけど、結構かっこいいよ〟って。
「沖島さん、これの正確な数値を測って記入し直してほしい」
佐々倉に見せられた紙には、文化祭で使用する物の情報が記載されている。その中のひとつ、『イートインスペース案内用のスタンド看板』のサイズに丸がついていた。
「あー……準備室に仕舞っちゃったから、あとで測る」
「今すぐに」
そんなに急ぐようなことでもないはずだと眉を潜める。夏休みにクラス全員でこうして学校で集まるのは貴重なことで、今はもっと時間をかけなければいけないことがたくさんあるのだ。
「でも先に他のことを進行したいし。てか、サイズざっくり書いたじゃん」
「僕は正確な数値を測った上で進めたい。でないと、本番直前になにかあったら困る」
少しも曲げる気がないらしく、淡々とした口調で話しながら佐々倉が私の机にメジャーを置いてくる。今すぐ測りに行くのは彼の中で決定事項らしい。
「はいはい。測ってくればいいんでしょ」
準備室はいろんなクラスの荷物が次々に積まれたり押しこまれていくため、その中から見つけて測る作業は少々面倒なのだ。だけど佐々倉を納得させないとしつこそうなので仕方がない。
「僕も行くから、ちょっと待ってて」
「え、佐々倉も行くの?」
「沖島さんひとりだとまた適当に測りそうだから」
じゃあ、最初から佐々倉が測りに行けばいいじゃんという言葉をぐっと飲み込んでため息を漏らす。まあ、私もざっくりと書いたのが悪い。
佐々倉は自分の席に戻り、ペンケースを開ける。おそらく数値を記入するためのペンを取りに行ったのだろう。すると、近くを通りかかった市瀬さんたちが佐々倉に声をかけた。
「佐々倉くん、うさちゃんシュークリームが好きなの?」
机の上に置いてある佐々倉の大好物のうさちゃんシュークリーム見て、市瀬さんを含めたクラスの女子たちが驚いている。あの堅物そうな佐々倉が、ファンシーなおやつを好んでいるのは意外だと感じるのは頷けた。あまりにもミスマッチすぎる。
「シールも全種類コンプリートしている」
何故か得意げに佐々倉が言った。そこで女子たちの笑いが起こる。
うさちゃんシュークリームにはシールがついていて、全八種類。それをたくさん持っている佐々倉はことあるごとに私たちリーダーへ配る資料に貼り付けてくるのだ。間抜けな顔をしたうさぎが『がんばっ!』などと言ってくるのがちょっとイラッとくる。
「佐々倉くんって可愛いね〜」
あの佐々倉が可愛い?と首を捻る。一緒にいることは多いけれど、一ミリも思ったことがなかった。
男子は可愛いと言われるのは複雑なのかと思いきや、本人は表情を崩すことなく真面目な顔で「ありがとう」と返している。その反応はどうなのかと呆れてしまう。けれど、そういうところが佐々倉らしいのかもしれない。
「ねえ、佐々倉って可愛いの?」
近くで今後の制作スケジュールを立てている古松さんに聞いてみると、固まってしまった。たぶんこれは真剣に考えている。人と話すことが得意ではない彼女なりに、必死に言葉を探しているのだろう。
少し間を置いてから、古松さんが口を開いた。
「……ギャップが可愛いってことじゃないかな?」
「ギャップねぇ」
男子がああいったファンシーなものが好きだったら意外だとは思う。でも例えば、爽やか系男子の石垣が持っていたら彼女の趣味かと疑われそうだ。佐々倉はそういったことに無縁そうだからこそ、一番ギャップがあるかもしれない。
「佐々倉くんはなんていうか……とっつきにくそうだから、可愛いものが好きだったり、シールを集めているのを知ると親しみが湧くのかも」
「なるほど」
少し前までは佐々倉と話すことすらなさそうだった市瀬さんたちが和やかな雰囲気で笑っているのを見て、確かにそういう効果はありそうだと納得した。
うさちゃんシュークリームに関する話が終わったらしく、佐々倉がこちらへ歩み寄ってくる。
「沖島さん、準備室に行こう」
私はメジャーを握り、じっと佐々倉を見上げた。愛想なんて欠片もなく、どちらかといえば冷たそうな印象を覚える。やっぱり可愛いとは思えない。
ふたりで廊下を歩いていると、急に佐々倉が「あ!」と声を上げて立ち止まった。
「なに? どうしたの」
何事かと身構えてしまう。しゃがみ込んで床に手を伸ばした佐々倉は、指先になにかをのせて私に見せてくる。そこには赤と黒の小さな物体がいた。
「てんとう虫だ」
「あ、うん……だね」
よく気づいたなと思いつつ、ちゃんと空いている窓から逃してあげている佐々倉の姿をぼんやりと眺める。
「佐々倉ってギャップがあるらしいよ」
「それは初めて言われたな。中学の頃は、真面目でメガネ以外特徴がないって言われてた」
佐々倉の言う通り、真面目そうなメガネ男子という印象が最初はあった。だけど足元の虫を大事そうに指にのせて逃してあげたり、ファンシーなものが好きだったり、第一印象とは結構違っている。
「それでもいいって思っていたけど、最近は沖島さんとか石垣たちが羨ましいと思うようになったな」
「なんで? 石垣は……まぁ男女に人気あるし、羨ましがられるのはわかるとして。私のどこが羨ましいの」
むしろ私はああはなりたくないと思われる側な気がする。言葉はキツいし、人とのコミュニケーションはいまだに得意ではない。友達だって少ない方だ。
「自分を持っていて、かっこいいところ」
「そんなの佐々倉だって持ってるじゃん」
文化祭の準備で誰かと衝突したり問題に打ち当たっても、誰よりもブレないのは佐々倉だと思う。
「僕はルールに囚われているだけで、沖島さんたちみたく意志の強さはあまりない」
再び歩き出しながら、私は佐々倉の言葉に耳を傾ける。誰かの話に対して自分の考えを言うことはあっても、佐々倉自身の話をしてくれることは今までなかった。なので、これが初めて聞く彼の本音のように感じる。
「佐々倉は自由が羨ましいんじゃない」
「自由?」
「ルールを常に守ろうとしてる佐々倉は、心のどこかで自分が不自由だと思ってんじゃないの」
「……そうかもな」
私には強い意志を持っているように見える佐々倉も、なにかしら抱えているものがあるようだった。ただ相談事には不向きな性格な私は、佐々倉の言葉に隠された感情を掬い上げて、心を軽くするようなうまい言葉は浮かんでこない。
「うちらのクラスがまとまってるのは、遠藤さんや石垣たちの声がきっかけだったけど、佐々倉が細かいところまでちゃんと見てくれているおかげで順調に進んでるじゃん」
私にでもわかるのは、この人がいなければ文化祭準備は今ほど順調には進んでいないということだ。だから誰かを羨ましく思うことがあっても、佐々倉は佐々倉のままでいい。私はそうであってほしい。
「てかさ、佐々倉って個性強くない? 小姑みたいにうるさいのに真顔でボケるし、ファンシーなおやつ好きだし」
「真顔でボケたつもりがない……」
「とにかくさ、佐々倉はおもしろいよ。まあ、面倒なときもあるけど」
「沖島さんは僕を上げて落として楽しんでるよな」
上げて落としている気はない。そういう佐々倉だから、私は一緒にいて楽しいのだ。それにこうして誰かと気楽に話せるようになったのは、佐々倉たちのおかげ。入学当初は私の言葉で誰かを傷つけたり、嫌われることを恐れて、ヘッドフォンで周囲の声を遮断していた。だからあの頃の私に教えてあげたい。もう少ししたら、私の言葉を必要としてくれる人たちができるよって。
準備室に着いて、積み上げられている物の隙間を通っていくと、私たちのクラスのスタンド看板を発見した。測れるように周りの荷物を少し動かしてから、メジャーの先を佐々倉が持って、本体を私が持つ。
「そうそう、あとさ」
先ほどの会話に追加して、私の思っていることを口にする。
「手を抜かずに頑張ってる佐々倉はかっこいいと思う」
静まり返ってしまい、妙な気まずさに包まれる。普段は会話のキャッチボールが速い佐々倉の反応が鈍いことが原因だ。
「……どうも」
「なにその素っ気ない返答。さっき可愛いって言われてありがとうって即答してたくせに」
不満だったのかと佐々倉を見やると、驚きの光景にあやうくメジャーを落としそうになってしまった。
「あ、いや……言われ慣れてないからびっくりした」
そう言って視線を逸らした佐々倉の耳は、ほんのりと赤くなっている。
なにその反応。そんな佐々倉知らないんだけど? と心の中で文句のような言葉が溢れ出てくるものの喉の奥で詰まって出てこない。
表情は相変わらず崩さないくせに、隠しきれていない佐々倉の感情を見つけてしまって、私にもその感情が伝染していく。心臓が大きく弾むように鼓動を繰り返し、頬が熱い。
「冗談だけど」
苦し紛れの一言を足すと、佐々倉が顔を上げた。そして何故か不服そうにわずかに眉を寄せる。
「……沖島さん、上げて落とさないでほしい」
私の発言で一喜一憂する佐々倉は珍しくて、目に焼き付けるようにまじまじと観察してしまう。表情をあまり崩さないので、感情の振れ幅が小さいように思っていたけれど、わかりづらいだけだったのかもしれない。
「あとメジャーもっとピンと張って。正確な数値じゃなくなる」
「はいはい。えーっと65センチかな」
「いや、64.8センチだ」
「細か!」
またいつか機会があれば、もう一度くらい言ってみようかと思う。
〝佐々倉は面倒だけど、結構かっこいいよ〟って。

赤でもなく青でもなく
夕焼け檸檬の文化祭
- 著:丸井とまと
- イラスト:まかろんK
- 発売日:2021年9月18日
- 価格:759円(690円+税10%)
書店でのご予約はこちらの予約票をご利用ください